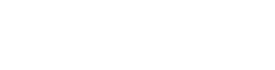コロナ発生から5年、企業のハイブリッド戦略はどのように変化してきたか
仕事とワークスペースをメインテーマとする世界的な知識ネットワーク「WORKTECH Academy」(ワークテック・アカデミー)は、グローバルトレンドを俯瞰する多彩な記事を発表している。今回はそのなかから、2024年第4四半期トレンドレポートの特別版「Company Close-up: how are employers really handling hybrid?」を抜粋し翻訳・編集して紹介する。
2019年末、前例のない公衆衛生上の危機が発生し、仕事や職場の将来の方向性に永続的な影響を及ぼした。パンデミック発生から1年後、ワークテック・アカデミーは、ハイブリッドワークに適応するために企業がどのようなワークプレイス戦略を採用すべきかを考察し、コロナ禍における組織を以下の6つのアーキタイプに分類した。
① 選択の推進者(Choice Champions):従業員に選択肢を与える企業
② テック投資家(Tech Investors):新テクノロジーへ投資する企業
③ 断固回帰者(Resolute Returners):オフィスに回帰する企業
④ ウェルビーイング推進者(Wellbeing Watchers):従業員のウェルビーイングを最優先する企業
⑤ データ活用者(Data Drivers):情報を駆使する企業
⑥ スペース編成者(Space Shapers):スペースを再構成する企業
本トレンドレポートでは、世界的なパンデミックがもたらす影響について特集を組み、5年という節目にこれら6つのアーキタイプを再訪し、その推移を確認する。当初の構想に忠実であり続けたのか、それとも状況の変化によって方向転換を余儀なくされたのか。特に大企業は、ハイブリッドワークにどのように対処してきたのか。
調査の結果、6つのアーキタイプのうち「選択の推進者」「テック投資家」「スペース編成者」では、多くの企業で戦略的な方向転換がみられた。一方で「断固回帰者」「ウェルビーイング推進者」「データ活用者」は当初の方針を堅持し、さらなる拡大フェーズへと進化していることがわかった。
1.選択の推進者(Choice Champions)
■「どこでも働ける時代」に立ちはだかる壁
パンデミック直後、従業員に柔軟性と選択肢を与えることは理にかなっていた。しかし近年、その道は険しいものになっている。
選択の推進者とは、パンデミックの混乱に対応し、柔軟な働き方を積極的に取り入れた組織である。これらの組織は柔軟性、選択肢、そして自律性を新たなワークプレイス戦略の柱とし、従来の9時から5時までのオフィス勤務モデルは時代遅れだと宣言した。従業員が多様な働く場所のなかから、どこでどのように働くかを自主的に選択できる、より洗練されたアプローチを構想した。
スポティファイ社やセールスフォース社、スラック社は、WFH(Work From Home、在宅勤務)モデルからWFA(Work From Anywhere、どこでも働ける)モデルへと急速に進化し、この動きの先駆者として注目された。この変化は、オフィスを予測困難な利用者の需要に対応できるように再設計する方法から、地理的な制約を超えて部分的または完全リモートポジションで人材を採用する方法まで、職場のあらゆる側面に重要な影響を与えた。
当初、選択の推進者は、人々を「オフィスの束縛」から解放し、より共感的で人間中心のアプローチを推進する取り組みとして高く評価された。多くの研究もこのアプローチを支持し、生産性を損なうことなく従業員のウェルビーイングを大幅に改善することを示した。
しかし、いくつかの成功事例があったものの、ここ5年間で選択の推進者は、徐々に高みから退くことを余儀なくされた。組織的な観点から見ると、ハイブリッドワークを適切に運用することは予想以上に難しいことが判明した。リーダーシップの進化はこのような急進的な変化に追いつかず、小売業界におけるオムニチャネルの導入に匹敵するような変革は、オフィス不動産の分野では実現しなかった。また、より柔軟な選択肢を提供するために人事やIT、不動産部門で必要とされる再構築の規模が大幅に過小評価されていた。
さらに、多くの従業員は、社会的孤立や過労を解消するためにオフィスへの復帰を望むようになり、特に若い従業員は、仕事上のネットワークを構築し、対面で同僚から学ぶことを求めている。その結果、選択の推進者のなかには、出社を強化する方向に舵を切った企業もある一方で、ハイブリッドワークの混乱を避けるために「リモートファースト」の働き方へと方向転換した企業も見られた。
■生産性に与える影響
選択の推進者のアプローチをめぐる大きな議論の一つは、生産性と人材確保への影響である。スタンフォード大学ニコラス・ブルーム氏、中国の学者ルオビン・ハン氏とジェームズ・レイング氏の共同研究では、在宅勤務とオフィス勤務を組み合わせたハイブリッドワークは、生産性を損なうことなく人材の定着率を向上させることが明らかになった。
この研究は、2021年から2022年にかけて、テクノロジー企業トリップドットコムの大卒中国人従業員1,612人を対象に、6ヶ月間のランダム化比較試験を行うことでハイブリッドワークの効果を検証したものである。対照群は週5日オフィス勤務の従業員とした。
その結果、 ハイブリッドワークは仕事満足度を高め、離職率を3分の1に減少させることがわかった。特に、非管理職や女性、通勤時間の長い従業員で、離職率の低下は顕著であった。さらに、全体的にも、主要な従業員サブグループにおいても、次の2年間の昇進に差は見られなかったことから、ハイブリッドワークは人事評価に影響を与えないことが示された。
■事例:選択の推進者が次にとった行動
オーストラリアのソフトウェア企業アトラシアン:従来のハイブリッドモデルを超えて、「Team Anywhere(どこでもチーム)」アプローチを採用している。出社日を定めず、従業員は自宅やオフィス、コワーキングスペースなど多様な働く場所を自由に選ぶことができる。また、円滑なコミュニケーションとコラボレーションを促進するためのツールとリソースを提供している。同社は信頼と自律性の強い文化を築くことを重視しており、従業員が自ら仕事のスケジュールや進め方をコントロールできる環境を実現している。
宿泊予約サイトエアビーアンドビー社:従業員が「Team Office(チームオフィス)」と自宅のどちらで働くかを選択できる仕組みを採用している。同社は、2022年9月にオフィスへの復帰を命じる決定を大幅に撤回し、全面的に自律的な働き方に移行した。ブライアン・チェスキーCEOは、柔軟な働き方を成功させるための主要な要素として信頼を挙げているが、完全リモートのチームでは孤立感や孤独感を感じる可能性があることも認識している。そのため、チームの集まりやオフサイトミーティング、ソーシャルイベントを定期的に実施している。また、従業員は自宅やオフィスの2択だけでなく、世界中どこからでも働くことができる。何より魅力的なところは、どこに引っ越しても給与が変わらない点だ。
大手テック企業マイクロソフト:柔軟な働き方には「一律の正解」がないことを理解しており、ハイブリッドワークの決定権を各マネジャーやチームに委ねている。同社は、ワークプレイス(物理的な場所)、勤務地(地理的な場所)、勤務時間という3つの次元にわたる柔軟な働き方を提供している。同社の求人情報には、ハイブリッドワーク施策とこれら3つの次元に関する情報が明記されており、候補者はジョブポジションにおける柔軟性の程度について採用担当者と話し合うことができる。また、同社は、従業員が自分にとって最も適した時間帯に働くべきだと考えている。
消費財大手ユニリーバ社:柔軟な働き方を、企業の持続可能性に向けた長期的なコミットメントの一環として捉えており、従業員が「いつでもどこでも仕事ができる」ように適応可能な働き方施策やテクノロジーを提供している。従業員のワークライフバランスを支援するため、ジョブシェアリングや時短勤務などの制度を正式に導入している。2021年に、オフィススペースの最適な活用方法に関するガイドラインを発表し、柔軟性を提供しつつも、勤務時間の40%以上をオフィスで過ごすことや、オフィスへ24時間以内に通える「合理的な」範囲に住むことなどを求めている。
2.テック投資家(Tech Investors)
■仮想空間から業務プロセスへ
パンデミック時に仮想現実に注力していたテック投資家は、現在、ハイブリッドワークの課題を解決するためにAIに目を向けている。
テック投資家とは、パンデミックを契機に、職場のデジタル化を推進した組織である。これらの組織は、デジタルと物理的な世界をシームレスに融合させることを目指すAR(拡張現実)やVR(仮想現実)といった新興テクノロジーに賭け、メタバースにおける優れた職場体験の創造に注力してきた。
アクセンチュア社やPwC社、フィデリティ・インターナショナル社など主要な専門サービス企業は、従業員が物理的に離れていたパンデミック当時、社内のつながりを向上させるためにこれらの仮想空間に投資していた。しかし、パンデミック発生から5年が経った今でも、メタバースのような概念はまだ浸透していない。ワークテックロンドン2024の基調講演者である著作家アジェイ・チョウダリー氏は、メタバースを「メー(meh)タバース」(*meh:無関心を表す間投詞)と表現した。
ARやVRの普及が停滞するなか、テック投資家は仮想空間よりも、業務プロセスのデジタル化に関心を移し、AI(人工知能)に目を向けている。戦略コンサルティング企業ニューバンテージ・パートナーズの2022年の調査では、92%の大企業がデータとAIへの投資効果を達成したと回答し、2017年の48%から大幅に増加した。AI導入に伴う巨額の投資も行われている。ゴールドマン・サックス社は、2025年までに世界全体のAI投資が2,000億米ドルに達する可能性があると予測しており、この技術の経済的な重要性がますます高まっている。
しかし、AIへの急速な投資とその統合には課題も伴い、特に労働力の面で顕著である。AIに投資する企業は、データ分析の高度なスキルを持つ人材を要しており、スキルのギャップが拡大している。テック投資家は、自動化による生産性の向上に焦点を当てているが、同時に従業員のリスキリングやスキルアップにも投資する必要があるだろう。
■AIが業績に与える影響
アクセンチュア社が2024年に発表した「生成AIによる企業オペレーションの再創造」レポートによると、74%の企業が生成AIと自動化への投資効果が「期待通り」または「期待以上」であると回答した。また、63%の企業が2026年までにこれらの分野への投資を拡大し、さらなる機能強化を図る予定であることが明らかになった。
さらに同レポートによると、AI主導の業務プロセスを導入している企業の割合が、2023年の9%から2024年には16%へとほぼ倍増しており、これらの企業は同業他社と比較して、収益成長率が2.5倍、生産性が2.4倍、生成AI活用事例の拡大における成功率が3.3倍であった。
「変革に向けた準備が整っている」とされるこれらのテック投資家は、他の企業よりも迅速に行動し、生成AIの効果を企業活動全体に拡大させている。ただし、この急速な進展は将来的に課題を引き起こす可能性も秘めている。
同レポートによると、AI導入の初期段階にある企業の8社に1社が、人材変革に向けた戦略を策定していない、人材ニーズを満たす計画がない、新たな人材の確保が進んでいない、生成AI主導のワークフローに対応するための研修を整備してない、などの課題を抱えていることが判明した。さらに、経営層の3分の2以上は、AIと生成AIの進歩が早すぎて、自社の人材育成が追いつかないと回答している。
■事例:テック投資家が次にとった行動
アマゾンウェブサービス(AWS)社:新しいAIスーパーコンピューター「Ultracluster(ウルトラクラスター)」の開発計画を発表した。このスーパーコンピューターは、同社独自の技術を活用してAI能力を強化し、既存のソリューションに代わる選択肢の提供を目指している。
セールスフォース社:自律型AIエージェント「Agentforce(エージェントフォース)」を導入し、IBM社などの大企業からも支持を得ている。エージェントフォースは人間が介在することなく、AIが自律的にタスクを実行し、意思決定を行うことができる自律型AIエージェントのプラットフォームである。この技術は顧客体験の向上や対話のパーソナライズ、リアルタイムのフィードバック提供、手作業の自動化などに活用されている。
会計事務所大手KPMG:業務全体にAIを導入し、会計や税務、アドバイザリー業務に携わる従業員がChatGPTやCopilotなどのAIツールを活用できるようにしている。この統合は作業スピードと運営効率の改善を目的としている。
総合コンサルティング企業キャップジェミニ:イノベーションと効率化を推進するため、生成AIを中心としたAI技術を自社の運営や顧客向けサービスに積極的に統合している。また、「生成AIラボ」を設立し、新しいAIテクノロジーの研究と実装を行っている。このラボは同社の「AI Futures」ドメインの一環として運営されており、AIの進歩を理解し、それをビジネス全体に適用することを目指している。
3.断固回帰者(Resolute Returners)
■オフィス回帰で断固たる決意を示す
多くの批判を受けながらも、従業員をオフィスに戻す方針を強硬に推し進める企業が増えている。
断固回帰者は、パンデミック直後から積極的にオフィス回帰を推進し、以来その勢いを崩していない。これらの企業は、全従業員をオフィスに戻すことが企業文化やイノベーション、学習、生産性を向上させる最善の方法であると考えており、強制オフィス回帰が従業員にどれほど不評であっても、その立場から一歩も譲るつもりはない。
ゴールドマン・サックス社デイビッド・ソロモンズCEOは、リモートワークは「異常」であり是正する必要があると述べた。断固回帰者の代表格にはサー・ジェームス・ダイソンや、JPモルガン・チェース社CEOジェイミー・ダイモン氏、イーロン・マスク氏など世界で最も有名な男性経営者が含まれる。かつては自律的な働き方を推進していた企業でさえも、より強硬なオフィス回帰方針に転じるケースが増えている。
例えば、グーグル社は出社状況をより厳しく管理する方針に変更して物議を醸している。同社の元CEO兼会長であるエリック・シュミット氏は、AI分野での優位性を失った原因が従業員のハイブリッドワークにあると述べ、「グーグルは勝つことよりも、ワークライフバランスや早く帰宅すること、在宅勤務の方が重要だと判断した」と指摘した。また、アマゾン社も断固回帰者に加わり、2025年1月から従業員に週5日の出社を義務付けると発表した。同社は、小売や物流、倉庫など現場で働く従業員と同様に、本社の専門職も完全出社する必要があると強調している。
断固回帰者は、物理的なワークプレイスがビジネスを繁栄させるために不可欠であり、従業員が同じ場所で働くことがコラボレーションや学習の文化を構築するうえで重要だと考え続けている。オフィス回帰の義務化がより若者中心かつ男性中心で、多様性に欠けた労働力を生み出すという研究者からの批判があるにも関わらずだ。一方でこれらの企業はオフィスを文化や創造性の中心地とするために、大幅なアップグレードや再計画、リニューアルが必要であることも認識している。
資金力のある断固回帰者は、すでに最先端のワークプレイスデザインへの投資を進めている。著名な組織心理学者キャリー・クーパー教授は、社会学の観点から彼らを「現代の恐竜」と表現しているが、より安全で健康的で人間中心のオフィス設計が広く採用される可能性も示唆されている。
■イノベーションへの効果
断固回帰者は、同じ場所に仕事仲間が集まって働くことでイノベーションが促進されると強く確信している。イノベーション理論では、画期的な発見を促進する要因として、社会的ネットワークやチームの役割が強調されている。ジェームス・ダイソン氏やイーロン・マスク氏は、この主張を繰り返し動員しており、研究でも裏付けられている。
ピッツバーグ大学とオックスフォード大学の研究者は、過去50年間に世界中で出願された2,000万件の論文と400万件の特許出願を分析した結果、「あらゆる分野、時期、チーム規模にわたって、リモートチームの研究者は、現場で働く研究者に比べて画期的な発見をする可能性が一貫して低い」ことを明らかにした。
この研究では、分散したチームメンバー間のコラボレーションが、体系化された知識を必要とする後期段階の技術的タスクに集中することが示された。一方で、新しいアイデアの考案や研究の設計など、知識が暗黙的である概念的なタスクにおいては、コラボレーションを行う可能性が低いことがわかった。研究者らは、「近年のデジタル技術の目覚ましい進化にもかかわらず、リモートチームはメンバーの知識を統合し、革新的な新しいアイデアを生み出す可能性が低い」と結論付けている。
■事例:断固回帰者が次にとった行動
英国薬局チェーンであるブーツ社:本社従業員3,900人全員に週5日出社を命じた。しかし、セブ・ジェームズCEOは、厳格な指令に加え、オフィスを「より楽しく刺激的な場所」にするという約束をしている。本社の環境改善策として、高速Wi-Fiの導入や、質の高い食事の提供、集中スペースの増設、駐車場の改善などが予定されている。
米国大手銀行JPモルガン・チェース:リモートワークの信頼性に疑問を投げかけ、大手金融サービス企業の中でも強硬な姿勢を示している。ジェイミー・ダイモンCEOは「どうやって文化と人格を築き、どうやって正しく学ぶのか」と疑問を呈している。現在は柔軟なポジションが一部残されているものの、シニアスタッフには週5日の出社を求めている。一方、2025年に完成するミッドタウン・マンハッタンの新本社は、最先端の設備と高いサスティナビリティ評価を誇り、「通勤の価値を高める」職場環境を目指している。
英国スーパーマーケットチェーンのアスダ社:厳しい市場状況に対応するため、人員削減や事業再編を実施し、2025年1月からリーズ市とレスター市のオフィスに所属する数千人の従業員に週3日以上の出社を義務付けた。働く環境を改善するため、質の高い食事の提供や居心地の良いアトリウム、ミーティングスペースや集中スペースの増設、トイレのアップグレード、新しい椅子の導入、内装の刷新、さらに敷地内にコンビニエンスストア「Asda Express(アスダエクスプレス)」を設置することを約束している。
アマゾン社:2025年1月から全従業員に週5日出社を義務付ける方針を発表し、アンディ・ジャシーCEOは「コロナ禍前のような勤務体制に」戻す必要性を強調した。同社は全員にデスクを提供することで打撃を緩和しようとしているが、スタンフォード大学ニック・ブルーム教授は、アマゾン従業員の30%がこの変更を理由に退職する可能性があると予測している。元ツイッター社欧州副社長で英国の労働文化専門家であるブルース・デイズリー氏は、アマゾン社の新たな厳しい出社方針が「若く、白人中心で、男性比率の高い組織」を生み出すだろうと指摘している。
4.ウェルビーイング推進者(Wellbeing Watchers)
■表面的な取り組みから科学的根拠に基づいたアプローチへ
ウェルビーイングをワークプレイス戦略の中心に据える企業は増加しているが、やる気のない従業員に対して本質的な解決策を提供することには注意が必要である。
ウェルビーイング推進者はパンデミックを機に、より良い業績を達成するため、従業員の健康とウェルビーイングを企業戦略の核に据えることを決意した。これらの組織は、世界的な調査で明らかになった従業員エンゲージメントの低下に注目し、対処するために共感重視の戦略を採用した。新たなリーダーシップモデルの導入やメンタルヘルスプログラムの提供、音響環境の改善や人間工学に基づく家具の導入など、ウェルビーイングを推進するオフィス設計に取り組んでいた。
健康的なアプローチの初期採用者としてはネットフリックス社やEY社、セールスフォース社が挙げられる。これらの企業は、従業員のウェルビーイングを向上させるためのサービスを提供し、従業員アンケートを活用して課題を把握した。オフィスで従業員の健康状態を直接確認する機会が減るなか、従業員のウェルビーイングをサポートするための選択肢と柔軟性を提供しようとした。また、ストレス軽減やエンゲージメント向上に効果的とされる共感的なリーダーシップの導入にも取り組んだ。
パンデミック発生から5年が経過した現在、職場におけるウェルビーイングへの取り組みはさらに発展し、企業はこの概念を積極的に取り入れている。しかしその焦点は、ジムやスパなど場所に依存するがゆえに柔軟性に欠ける、高価なアメニティを提供する取り組みから、人材と施策に移行している。身体的・精神的・社会的な健康に総合的に取り組むホリスティックウェルネスが注目されている。
ハイブリッドワークの普及や従業員の自律性の高まりに伴い、より多様で個別化されたウェルネスプログラムが増加した。しかし、おそらく必然的に、職場の健康に対するこうした強調は、一部では「Wellness gloss(表面的なウェルネス)」として批判されることもある。
職場におけるエンゲージメント低下が続くなか、より多くの従業員がその場しのぎの解決策や象徴的な行動ではなく、苦痛や不満の根本原因に対処する、より深く科学的根拠に基づいたアプローチを求めている。
■ウェルビーイングの主な推進要因
ウェルビーイングプログラムの成否はリーダーシップの支持に大きく依存する。単なるパフォーマンスにとどまらず、より深い文化的問題に真剣に取り組む必要がある。
英国政府の取り組みである『What Works Wellbeing』は、2014年から2024年までの10年間にわたり、この分野の研究を行ってきた。イーストアングリア大学が主導し、エセックス大学、シェフィールド大学、レディング大学と連携したコンソーシアムの一環として、働き方の変化がウェルビーイングに与える影響や、職場でのウェルビーイング、職場文化、学習の役割などに関する膨大なデータを分析した。
2017年には、ウェルビーイング戦略があると回答した英国企業はわずか30〜40%にとどまったが、現在では65%にまで拡大し、分野も医療や教育、警察、法律事務所、銀行など多岐にわたる。
同研究では、ウェルビーイングプログラムを実施する際に考慮すべき5つの原則が提案されている。コミュニケーション、一貫性、コミットメント、継続性と創造性である。
さらに、職場におけるウェルビーイングの主要な5つの領域として、人間関係、セキュリティ(安全性)、目的意識、環境および健康が提示されている。このフレームワークは、職場のウェルビーインを向上させるために、企業が資源をどの領域に重点的に投入すべきかを特定するのに役立つ。
■事例:ウェルビーイング推進者が次にとった行動
製薬大手GSK社:2024年6月にロンドン西部郊外のキャンパスからロンドン中心部にある15万平方フィートの最先端本社に移転し、科学的根拠に基づくワークプレイス変革を実践した。この移転は、従業員のウェルビーイングと生産性を促進するために科学とデザイン、テクノロジーを統合し、世界で最も健康的な職場を創出するという同社の野心的な目標を反映したものである。同ビルの9階を従業員のウェルネス専用フロアとし、無料のフィットネスクラスや最先端のジム施設を提供している。1階のレストラン「ザ・オランジェリー」は「農場から食卓へ」をコンセプトに掲げ、地下には1.4エーカーの農場に相当する都市型農場を備えている。
HSBC銀行:従業員のメンタル回復力を高めるためのマインドフルネスプログラムに取り組んでいる。70の拠点に20万人以上の従業員を擁する同行のウェルビーイング戦略の中核は、グローバルなマインドフルネス拠点づくりだ。職場におけるストレスの根本原因に取り組むことを目指しており、そのプログラムの成功はデータの収集と活用、テンプレートとガイドラインの作成、そして模範的なリーダーシップに支えられている。マインドフルネスは同行の戦略の重要な一部であり、「脳にやさしい」職場環境づくりが進められている。
セールスフォース社:従業員が健康的な生活を送るための福利厚生やリソース、サポートへのアクセスを提供する仮想プラットフォーム「Camp B-Well」を導入した。プログラムの1つである「B-Well Together(ともに実現するB-Well)」という動画シリーズでは、精神的、身体的、社会的なウェルビーイングの専門家からの先進的な考え方やアドバイスを提供している。
グーグル社:長年にわたりウェルネス分野をリードしてきた同社は、敷地内のヘルスケアやフィットネス施設、パーソナライズされたウェルネスサービスなど、従業員に幅広い福利厚生を提供し続けている。「フード・アット・グーグル」と呼ばれる同社の食事プログラムは、食事が人々を結びつけるだけでなく、全体的なウェルビーイングを向上させるという考えに根ざしている。無料の食事だけでなく、同社は従業員にウェルネスプログラムや包括的な健康手当も提供している。
マイクロソフト社:リモートワークの普及に伴い、ホリスティック・ヘルス・デー(*フィジカルヘルスだけでなくメンタルヘルスのためにも利用できる病欠)を導入し、すべての管理職に「思いやりのある」マネジャーになるための研修受講を義務付けるなど、ウェルネス施策を拡大している。また、敷地内に最先端のフィットネスセンターを設置し、従業員はグループフィットネスクラスやパーソナルトレーニングサービスを利用できる。
5.データ活用者(Data Drivers)
■生き残り戦略から成長戦略へ
データ活用者は当初、ワークプレイス戦略に役立つ洞察を得るためにデータを活用していた。しかし今では、データ錬金術から精密分析へと進化を遂げている。
コロナ禍中、データ活用者は、仕事の世界の激動を乗り切るために分析能力を素早く動員した。そして現在、データの役割は生存のためのツールから企業戦略の基盤へと進化している。企業はもはや危機への対応にとどまらず、データを活用して予測し、革新や成長を促進している。
IBM社が提唱した「データ錬金術」という概念は、相関関係や実用的な洞察をワークプレイス戦略に反映させるプロセスである。パンデミック直後から多くの企業はこのプロセスに注目し、今日ではこの実践は、AIや機械学習の進歩に支えられ、精密分析へと進化している。データは単に現在を理解するためだけでなく、将来のシナリオをモデル化し、人材戦略やワークプレイス設計、資源の最適化などの意思決定を促進するためにも活用されている。
一方、多くの企業では、分析戦略と企業目標の整合性に依然として課題を抱えている。マッキンゼー社の報告によると、企業の約70%がこれらの要素の統合に苦戦している。しかし、パンデミック後のデータ活用者はこれらの統合を円滑に実現し、データを企業活動のほぼすべての層に組み込んでいる。彼らは予測分析を活用してスペースやエネルギーの使用を最適化するだけでなく、従業員のエクスペリエンスを個別に設計し、ハイブリッドな職場環境におけるエンゲージメントと人材維持を確保している。
コロナ禍中のデータ活用は、稼働率の追跡や健康リスクの管理、コンプライアンスの確保など、安全性に重点を置いていたが、今日はより戦略的な方向に進んでいる。データ活用者は、従業員のウェルビーイングの向上や、不動産の意思決定への情報提供、ESG目標のサポート、ハイブリッドワークモデルの効果的な導入のためにデータを活用している。
データ活用者は、分析をサイロ化された機能ではなく、共有の責任とする文化を醸成し続けている。データツールへのアクセスを民主化することで、浸透性を促進しつつ、あらゆるレベルの従業員が情報に基づいた意思決定を行えるようになる。一方で、データの安全性と倫理に関する懸念は依然として残っている。急増したデータ収集は従業員のプライバシーやAIの偏りに関連するリスクを高める要因となっている。これに対し、企業は強固なガバナンスフレームワークを採用し、透明性を高め、倫理的なAI開発を優先することで対処している。
今日の環境において、データ活用者は課題に最も迅速に対応し、機会を予測・創造する能力を備えている。これにより、データは未来の職場において中核的な資産として位置づけられている。しかし同時に、データ活用のリスクにも注意を払う必要がある。
■未来を切り拓くデータ先駆者
米国経営学誌『ハーバード・ビジネス・レビュー』とグーグルクラウド社の共同研究では、360人以上の経営幹部を対象に調査を行い、企業がデータ主導の意思決定に向かう傾向が強まっていることが明らかになった。また、データと人工知能(AI)への投資を先行する企業(以下、「データ先駆者」)は、同業他社に比べて収益性が高く、革新性も優れていることが示されている。
同研究から得られた主な洞察は、以下の通りである。
- 収益性とイノベーションの向上:データ先駆者は、AIとデータ分析を活用して意思決定を促進し、それが収益性の向上とイノベーション能力の強化につながっている。
- 製品開発の加速:データ先駆者は、データから得られる洞察を活用して新製品の開発を加速させ、市場投入までの時間を短縮し、競争優位性を確立している。
- 顧客満足度の向上:データ主導の戦略を統合することで、顧客のニーズをより深く理解し、満足度とロイヤルティの向上を実現している。
同研究では、こうした成果を達成するためには、データを戦略的に活用することが非常に重要であると強調されている。また、情報に基づいた意思決定の文化を醸成するために、組織全体でデータへのアクセスを民主化することの重要性が提唱されている。
■事例:データ活用者が次にとった行動
米国不動産デペロッパーRXRリアルティ:テナント体験を向上させるために、データ分析を業務に統合した。デジタルプラットフォームを開発し、ビルの稼働状況、空気の質、清掃スケジュールなどの情報をリアルタイムでテナントに提供している。この透明性により、より安全で快適な環境を実現し、テナントの期待に応える職場環境を構築している。
グローバル不動産サービス企業コリアーズ:AI技術を活用し、WiFiデータを通じてオフィスの稼働率を監視・分析している。このアプローチにより、企業はワークスペースの利用状況を理解し、オフィススペースの要件に関する意思決定に活かし、リソースを有効活用することができる。
多国籍企業ジョンソン・エンド・ジョンソン:AIを活用して従業員の能力を評価する「スキル推論」を導入することで、的確なトレーニングや能力開発プログラムを設計している。この戦略は、社内の人材流動化を促し、従業員の定着率を向上させるとともに、変化するビジネスニーズに対応できる人材力の確保に貢献している。
DBS銀行:AIとデータ分析に大規模な投資を行い、超パーソナライズされた洞察と提案を顧客に提供することで、より良い金融上の意思決定を支援している。また、従業員にビッグデータと分析のトレーニングを実施することで、データ主導の文化を醸成し、顧客サービスを向上させるとともにイノベーションを推進している。
6.スペース編成者(Space Shapers)
■大幅削減からスマートな空間創造へ
スペース編成者は、パンデミック初期にオフィススペースの大幅な縮小を予想していたが、現在では、質を重視したより穏健な戦略を採用している。
スペース編成者は、パンデミックを職場環境の変化にあわせて不動産ポートフォリオを再構築・合理化する機会と捉えていた。チームワークやコラボレーションを優先したスペース戦略を採用し、より創造的なアプローチをとった企業もあった一方で、多くの場合、オフィス面積の大幅な削減に終始した。
コロナ禍直後、金融やメディア、経営コンサルティングなどの専門的サービス企業は、柔軟な働き方施策と連動してオフィススペースの削減や再構築を検討していた。コロナ禍発生から1年後、オフィススペースが40%削減されると予測され、リーズマン社は「スペースは半分、体験は2倍」とさえ語っていた。しかし、オフィスへの回帰が進むなかで、大規模なオフィス削減計画は撤回され、オフィススペースを大幅に縮小する動きは徐々に下火になっていった。
ハイブリッドワークの複雑さがより明確になるにつれ、オフィススペース削減の予測はまず20%に引き下げられ、さらにその半分となった。マッキンゼー社は、2030年までに世界全体でオフィス不動産の削減が約10%程度と予測している。これは、理想的ではないが、壊滅的な数字でもない。
企業は依然としてポートフォリオの削減を検討しているが、もはやスペースを削減することではなく、現在あるスペースをいかに効果的に機能させるかが重視されている。デザインやアメニティ、テクノロジーへの投資から、企業がオフィススペースの価値を認識しつつ、従業員のニーズや行動の変化に応じてスペースを再構築しようとする動きが読み取れる。
アーバンランド研究所とPwC社の共同研究では、「オフィスの需要は最終的には高性能なビルに集中する」とされており、サステナビリティやテクノロジー、従業員の体験といった現代的な基準を満たす高品質なスペースが選ばれることを示している。この「質への逃避」は、急進的なスペース削減計画が頓挫する主な理由の一つである。
■都市に与える影響
スペース編成者のアプローチをめぐる課題の一つは、都市全体への影響である。オフィススペースの合理化とハイブリッドワークの組み合わせにより、中心ビジネス地区やショッピングセンターでの滞在時間が減少している。
マッキンゼーグローバル研究所のレポートによると、都心部のオフィスや商業施設の空室率の上昇に対抗するためには、都市がニューノーマルに適応し、自らもハイブリッドなアプローチを採用することが必要である。こうした「ハイブリッド化」を取り入れるために、複合用途地区の開発や、より適応性の高いビルの建設、多用途のオフィスや商業施設の設計などに優先的に取り組むことが求められるだろう。言い換えれば、スペース編成は、都市規模の次元へと波及しているのである。
同レポートでは、パンデミックが世界中の都市での働き方や買い物行動を劇的に変化させたと説明している。オフィスの稼働率や人流は回復が遅れており、特に低品質で古いビル(BクラスやCクラス)は需要が低下し、その結果、余剰のワークスペースが生じている。
しかし、スペース編成者は、ホスピタリティを重視した魅力的なワークプレイスを創造することで、オフィスの魅力を維持することができる。週ごとに変化する働き方に対応可能なモジュラー型スペースや、ハイブリッドな働き方と個々の嗜好を効率的かつデジタルに管理する方法を提供することは、重要な役割となるだろう。
■事例:スペース編成者が次にとった行動
エンジニアリング・コンサルティング企業アルカディス:柔軟な働き方に対応するために、ロンドンのフェンチャーチ・ストリート80番地に本社を移転した。この移転は、「どこで働くか」から「どのように働くか」に重点を移すもので、不動産戦略における根本的な変化を表している。移転後の新本社では、オフィス稼働率が50%から最大95%に大幅に向上したと報告されている。
ドロップボックス社:パンデミック後に在宅勤務方針を拡大し、全従業員がリモートワークを基本とする「バーチャルファースト」企業となった。対面での共同作業が必要な場合には、既存の不動産やその他のフレキシブルなスペースを活用することもできる。これらのスペースは「ドロップボックススタジオ」と名付けられ、コロナ禍以前にオフィスがあったすべての地域に設置される予定である。また、従業員数が多く、長期賃貸契約を交わしているオフィスには、専用スペースを維持している。
CBRE社:パンデミック後にロンドン本社「ヘンリエッタ・ハウス」を大規模に改装した。オフィススペース合理化の動きに逆らい、新社屋には、自然光が降り注ぐ2つのアトリウムと外庭が増設され、既存ビルの正味面積が45%増加した。同社は2011年からヘンリエッタ・ハウスを拠点としており、2036年まで新たにリース契約を延長し、進化する職場のニーズに対応している。
デロイト社:パンデミック以降、ロンドンのオフィススペースを約7万平方フィート拡張した。この拡張はパンデミック初期に導入された大幅な削減計画を覆すものであり、ロンドン拠点全体の面積は約18%増加した。同社のこの戦略は、コンサルティング業界全体でコロナ禍初期に計画されたオフィス縮小を撤回する動きの象徴的な例である。
関連記事
慣例を破る:未来の働き方を変革する8つのアイデア
慣例を打ち破り、未来の働き方が目指すべき方向性とは? 2024年に世界各地で開催されたワークテックカンファレンスの8人の基調講演者による、実践的なアドバイスを紹介する。
ソフトサービスが拓くビル事業の可能性
BIRTH LAB・BIRTH WORK 麻布十番/髙木ビル
つくって貸すだけではない、ビル事業とは? 人のチャレンジに伴走するコワーキングスペースの事例とコミュニティ形成の在り方を紹介する。