仕事と職場のグローバルトレンド2025「25のキーワード」(後編)
仕事とワークスペースをメインテーマとする世界的な知識ネットワーク「WORKTECH Academy」(ワークテック・アカデミー)では、グローバルトレンドを俯瞰する多彩な記事を発表している。今回はそのなかから、2025年1月に発表したトレンドレポート「The world of work in 2025」を紹介する。
レポートでは、「人」「場所」「テクノロジー」という切り口で、2025年に注目すべき25の主要トレンドを取り上げている。「人」に関する予測では、ハイブリッドで創造的なリーダーの育成、高齢化する人的資本、よりアクセスしやすいメンタリング、そして職場における神経多様性への取り組みなどが挙げられる。「場所」においては、職場の「活気指標」、関係性ベースの働き方の台頭、エクスペリエンスデザイン、ワーク・リゾート、さらに急速な気候変動に対応するための都市の回復力向上施策などが取り上げられている。「テクノロジー」のトレンドでは、ビデオ会議の向上や、職場での孤独感に対処するための有意義なつながりの創出に加え、「どこでもデジタル」と「デジタル・デトックス・ゾーン」の必要性が探求される。また、2025年における最も大きな変革の波としてAIの進化と新潮流が予測される。
前編に続き、後編では、以下の10キーワードについて解説する。
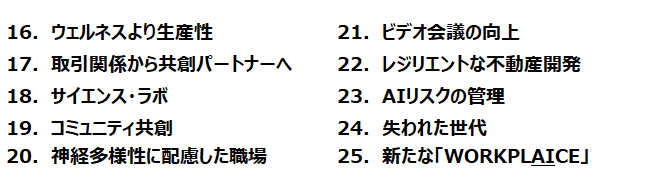
16.ウェルネスより生産性(Performance Over Wellness)
ウェルビーイングはより明確に業績と結びつく
パンデミック発生から5年が経過した今、企業は単なる職場のウェルビーイングではなく、デザインやその他の意思決定がパフォーマンスに与える影響により重点を置く方向へと転換しつつある。
ウェルネスから生産性への方向転換は、いくつかの要因によって加速されている。経済の低迷が続くなか、企業はこれまで以上に財務パフォーマンスの向上を求められている。
また、おそらくオックスフォード大学の研究者ウィリアム・フレミング氏の研究結果に影響を受け、企業はウェルビーイング施策への過去の投資がどれほど効果的であったかについて、慎重な姿勢をとるようになっている。同氏は、英国の233社の46,000人の従業員を対象に調査を行い、多くの企業が導入したメンタルヘルス施策が従業員に対してほとんど、あるいは全くプラスの効果がないことを明らかにした。
とはいえ、2025年に職場のウェルビーイングが重要視されなくなるわけではない。多くの企業にとって、ウェルビーイングは依然として重要な優先事項であり続けるだろう。ただし、心身の健康は、これまで以上に明確に業績と結びつけられるようになる。「パフォーマンスこそがすべて」という考え方が浸透し、生産性向上が期待できるエルゴノミック家具や概日照明、バイオフィリックデザインといった要素の需要が高まると予想される。
ウェルネスプログラムの価値を定量化したマッキンゼー社のレポートでは、職場の生産性を向上させるだけでなく、人材を惹きつけ、維持する観点からも「従業員の健康とウェルビーイングへの投資は理にかなっている」と指摘されている。
17.取引関係から共創パートナーへ(Transactional to Transformational)
デベロッパーと入居テナントが共創パートナーシップへ
ワークプレイスはもはや単なる作業スペースではなく、つながりや創造性、成長を促進する磁場へと進化している。2025年、商業デベロッパーはこうした理想を実現するうえで極めて重要な役割を果たす。デベロッパーと入居テナントの従来の取引関係は、人々を惹きつけ、夢中にさせる体験や目的地を共に設計する共創パートナーシップへと変化しつつある。
アンワーク社によると、この変化にはデベロッパーの役割の再考が必要である。単なるスペースの提供者ではなく、エクスペリエンス・キュレーターとして入居テナントのデータを活用し、適応的で革新的で人間中心の空間を設計することが求められている。この変革において、データの交換は重要な役割を果たす。デベロッパーはリアルタイムのフィードバックを活用することでワークプレイス環境を継続的に改善し、最適化することができる。
新規開発における主要なデザインの優先事項は、柔軟性、持続可能性、そしてテクノロジーの統合である。建物は、さまざまな活動をサポートするモジュラー式レイアウトや多機能スペースを備え、進化し続けるワークプレイスのニーズに適応する必要がある。同時に、バイオフィリックデザインや先進的な空気清掃システム、持続可能な素材などを活用し、より健康的で環境に優しい空間を創造することも求められる。
また、テクノロジーも新規開発において重要な役割を果たす。スマートビルシステムやAIを活用したツールなどの最先端インフラを導入することで、ワークプレイスは確実に未来に対応し、ハイブリッドワークモデルをサポートすることが可能となる。
デベロッパーは今、静的な建物ではなく、活気あるエコシステムを創出する機会を得ている。こうしたエコシステムは、コラボレーションやメンターシップ、創造性、そしてコミュニティの形成を促進する。デベロッパーは入居テナントと協力し、この変革的なアプローチを取り入れることで、従業員をオフィスに呼び戻すことを支援するだけでなく、生活を豊かにし、パフォーマンスを向上させる空間を創り出し、長期的な価値を提供できる。
18.サイエンス・ラボ(Science Labs)
2025年、ライフサイエンスの職場は変革の年を迎えるか
他の分野と比べ、多くの科学施設はいまだに技術的な機能性を最優先し、職場環境全体のエクスペリエンスがあまり重視されていない。
建築設計事務所BVNによると、この現状を変える必要がある。なぜなら、そこで働く科学者や研究者は、単なる白衣を着た博士ではなく、まず「人間」だからだ。私たちの健康を守り、病気と闘い、未来のためにイノベーションを牽引する彼らには、さまざまな実験を行うためのスペースではなく、最大限に活躍し、成長できる職場環境が与えられるべきである。
確かにラボは安全性や設備、構造、規格、リスク管理など、厳格な要件を満たさなければならない、複雑な空間である。しかし、それがコラボレーションや創造性、ウェルビーイングを促進する環境を犠牲にすべき理由になるだろうか。他の業界では、集中と相互作用を両立できる多様な空間づくりが進められている。それにもかかわらず、なぜこうした変革がサイエンスの職場に十分に浸透していないのだろうか。
理由が何であれ、現状では研究者たちは孤立した、機能性だけを重視した環境で長時間過ごしており、個人的な可能性も仕事上の可能性も制限されている。BVN社は、「ラボを単に科学が行われる場所としてではなく、科学を生み出す人々が真に繁栄できるエコシステムとして再構築する」という視点を提案する。
実際、研究活動には波があり、ラボで継続的な実験が必要なプロセスもあれば、機器の待機時間、培養、データ分析など一定の待ち時間が発生するプロセスもある。このリズムを活かして、ラボでの集中作業、データ分析、教育、コラボレーションを円滑に行き来できる環境を整えれば、よりダイナミックで充実した職場が実現できるだろう。こうしたアプローチを取り入れた施設も一部には存在するが、まだ普遍的なものには程遠い。
2025年こそ、ライフサイエンスの職場が「機能第一」のイメージを脱却する年になるだろうか。
19.コミュニティ共創(Community Co-Creation)
企業キャンパスは都市の社会インフラの一部になる
オフィスは周囲のコミュニティとどのようなつながりを築くべきか? 2025年には、イケア社やレゴ社などの大企業が自治体と協力し、「暮らす」と「働く」を融合させた人間中心の空間を共創することで、仕事と場所の関係が再定義されるかもしれない。
これは、従来の孤立した企業キャンパスから、社内の従業員同士だけでなく、周辺コミュニティとも有意義なつながりを育む統合型・多機能型のハブへの転換を意味する。多くの企業が、従業員が職場だけでなく周囲の環境ともつながりを感じることで、より充実した働き方ができることを認識し始めている。
自治体や都市計画専門家と連携することで、企業は職場の壁を越え、住宅や緑地、交通インフラ、コミュニティハブなどを取り入れたワークプレイス戦略を展開している。こうした取り組みの中心にいるのは従業員と家族、そして地域コミュニティであり、企業は職場での体験向上を図るとともに、持続的な社会的インパクトを生み出すことを目指している。
このアプローチの重要なポイントは、対象が従業員だけにとどまらない点にある。家族や地元企業、地域活動のためのスペースを統合することで、企業は社会インフラの充実を図り、帰属意識を醸成することができる。この共創により、従業員はより大きな目的と結びつきを感じる一方、地域社会は生活の質の向上や経済的機会の増加といった具体的な恩恵を受けることができる。イケア社の親会社であるインカグループは、従業員の体験を向上させ、強固な企業文化を築き、業務の効率化を図るために、こうした理念に基づいた多機能型ハブを構築している。
企業が持続可能性や社会的インパクトをますます重視するなか、この動きは「人と地球にとって有益な環境づくり」に対するコミットメントを示している。こうしたコミュニティ形成の潮流を牽引する先進的な企業は、ワークプレイス設計と企業責任の新たな基準を確立しつつある。
20.神経多様性に配慮した職場(Neuroinclusive Workplace)
多様なニーズに対応する感覚刺激のデザイン
注意欠如・多動症(ADHD)や自閉症、ディスレクシア(*読字障害)など、神経多様性への認識が高まるにつれ、企業は従業員全員に配慮した環境の必要性をますます認識するようになっている。研究によると、5人に1人は神経多様性があるとされるが、そのうち半数以下しか自覚しておらず、実際の割合はさらに高い可能性がある。
感覚刺激は神経発散型の人だけでなく定型発達の人にも有益な影響を与えるため、極端なニーズに対応したデザインはすべての人に利益をもたらす。建築設計事務所HOKのケイ・サージェント氏によると、インクルーシブデザインは単なる「配慮」にとどまらず、すべての従業員のために集中力を高め、ストレスを軽減し、生産性を向上させる環境を創り出すという。この先進的なアプローチは、企業の多様性を反映すると同時に、従業員のエンゲージメントや満足度、パフォーマンスを向上させることでビジネスの成長にも貢献する。
企業が優秀な人材を引きつけ定着させるためには、公平性やウェルビーイングを促進する、神経多様性に配慮した職場づくりが標準となるだろう。2025年には、先進的な企業がインクルーシブデザインと感覚処理技術を活用し、すべての従業員が活躍できる環境を構築していくことが期待される。
21.ビデオ会議の向上(Video Hegemony)
リモート参加者は会議でどうすれば主導権を取り戻せるのか?
コロナ禍以降、職場にはハイブリッド会議のためのモニターがあふれている。多くの人がオフィスに戻っているにもかかわらず、モニターの数は増え続けている。その理由の一つは、リモートワーカーにも公平な環境を提供し、画面越しの存在感を対面と同等にすることを目指しているためである。
しかし、近接性バイアス(*対面の人を無意識に優先する先天的傾向)を克服しようとする試みは、現在では十分に機能していない。例えば、モニターは部屋のどこからでも見やすいように、テーブルの短辺やすべての椅子がその方向を向いている座席の中央など「リーダーの位置」に配置されることが多い。しかし、これは、伝統的に会議の主導者が座り、議論をリードする役割を担ってきた場所である。
さらに、モニター上のリモート参加者の顔は対面の参加者と同じサイズで映し出すのが理想とされるが、実際にはリモート参加者の顔が通常より大きく映ることが多い。そのため、対面の参加者と自然に対話することが難しくなっている。
研究によると、地理的に離れた場所で働く人々をつなぐテクノロジーを開発する際には、同じ場所にいる従業員同士の断絶にも十分な配慮が求められる。また、ハイブリッド会議における「存在感」を高めるために、適切な照明や背景の工夫などの対策も推奨されている。
2025年には、ビデオ会議の体験を向上させる新たな取り組みが進むのだろうか? 今年もこのテーマが大きな注目を集めそうだ。
22.レジリエントな不動産開発(Resilient Real Estate)
過酷な気候が都市のあり方を変える
2025年初頭に、カリフォルニア州を襲った山火事や米国東海岸の暴風雪、英国全土の壊滅的な洪水など自然災害が相次いだ。深刻化する気候変動に対応するために、都市は経済活動とイノベーションの拠点として、人とインフラの両方を守るレジリエント(*回復力のある)な環境づくりを先導する必要がある。
建物だけで世界の二酸化炭素排出量の40%近くを占めているが、回復力の必要性は個々の建物にとどまらない。都市全体のエコシステムを見直し、ますます激化する気候変動に適応できるようにすることが求められる。
これには、持続可能な建築手法の採用や再生可能エネルギーシステムの統合、洪水・熱波・強風といったリスクを軽減するインフラの整備が含まれる。また、環境モニタリングやエネルギー利用の最適化を可能にするスマートテクノロジーを活用し、資材の適応的再利用を促進することも重要となる。
気候変動による災害が頻発するなか、地域に根ざした柔軟な都市政策は、通勤交通量と二酸化炭素排出量の削減に貢献し、回復力を高める鍵となる。住居、職場、生活利便施設が集積する複合用途地区を整備することで、エネルギーを大量に消費する交通システムへの依存を最小限に抑えることができる。さらに、都市全体で循環型経済の原則を導入することで資源の再利用を促進し、廃棄物の削減にも貢献できる。
都市のワークプレイスや大規模な企業インフラもその一翼を担うことになる。レジリエントなワークプレイスには、耐久性・耐候性に優れた素材や受動的冷却システム、洪水対策などの機能を組み込むことが重要である。デザインは美しさだけでなく、過酷な状況下での機能性にも配慮する必要がある。さらに、自動照明や温度制御、再生可能エネルギーの統合などの技術を活用することで、エネルギー効率を向上させ、将来の環境変化にも備えることができる。
都市が今どのような決断を下すかが、その将来の持続可能性を左右する。また、都市内の企業も、先進的な設計や方針を通じて気候の不確実性に適応する回復力を備えていくことが求められる。
23.AIリスクの管理(Managing AI Risks)
従業員の創意工夫を称賛しつつも、慎重に行動すべき
AIには業務の効率化や生産性向上の大きな可能性があることは明らかである。しかし、この流れを推進しているのは経営層ではなく、従業員自身である。正式な承認の有無にかかわらず職場でAIツールを活用するケースが急増している。リンクトイン社とマイクロソフト社の調査によると、従業員の75%が何らかの形でAIを活用している。また、AI利用者の78%は企業から公式にAIツールを提供されるのを待たずに、自らAIを導入している。
企業リーダーはこのトレンドにどのように対応すべきだろうか。変革と移転管理コンサルティング企業であるムーブプラン社は、「その答えはAIを積極的に活用する従業員を称賛することだ。ただし、リスクは慎重に管理する必要がある」という。
AIの普及により、企業はさまざまなリスクにさらされる可能性がある。誤用(エラー、偏見、誤った情報の拡散)、倫理的問題(プライバシー、公平性、説明責任)、法規制上の課題(AIはデータ保護法や著作権法の対象となる)など、懸念すべき点は多岐にわたる。
新しいテクノロジーは積極的に受け入れるべきだが、適切に管理された環境の下で活用する必要がある。2025年には、企業リーダーにとって、AIのメリットを最大限に引き出しつつリスクを最小限に抑えるという課題がさらに重要になるだろう。
24.失われた世代(The Lost Generation)
AIの二極化が若年労働者に及ぼす脅威
AIの台頭により、労働市場の二極化が進み、役割や給与、キャリアパスが再定義されつつある。JLL社のグズマン・デ・ヤルザ氏によると、「スーパー・エグゼクティブ・ディレクター」と呼ばれる新たなエリート層が出現している。彼らはAIを活用してかつてない生産性と効率性を実現し、破格の報酬を得ている。一方で、多くの労働者は自動化や人員削減、低賃金の仕事に留まり続けるリスクに直面しており、職場における公平性の格差が拡大している。
また、AIの急速な普及により、これまでキャリア形成の基盤とされてきた初級レベルのルーチンタスクが変容しつつある。この変化により、若手従業員が成長に必要な経験を積むことが難しくなっている。その結果、彼らはAIに取って代わられる職務と、これまで培う機会がなかったスキルを必要とするリーダー職との間で板挟みになり、「失われた世代」が生まれつつある。
この格差に対処するため、企業はこの新しい現実に備えて従業員を育成する方法を見直し始めている。特にAIリテラシーや感情的知性(EI)、リーダーシップなどの分野におけるアップスキリングやリスキリングへの投資が、この急速に広がる格差を軽減するための重要な戦略となっている。また、従業員がAI時代の職場で活躍できるよう支援する一環として、適応力や人間中心のスキルを強化するための資格取得や研修が優先されている。
2025年には、AIの導入だけでなく、それがすべての従業員にとって有益なものにすることが課題となるだろう。先進的な企業は、テクノロジーの革新と労働者の公平性のバランスをとり、スキルギャップを埋め、すべての従業員が学び、成長できる環境を整えることに注力するだろう。
25.新たな「WORKPLAICE」(The New Workplaice)
AIが2025年の破壊的トレンドの主役になる
AIは仕事の未来に多大な影響を与え、破壊的な変革の一つと見なされるだろう。AIには人間の努力を向上・補強し、さらには代替する可能性があり、2025年を迎える今、その潜在的な影響がようやく理解され始めたところである。
自動化の進展により雇用が失われ、その結果、多くの人々が職を失う可能性が議論されるなかで、その影響を抑えるためにユニバーサル・ベーシックインカム(*政府が全国民に対して決められた額を定期的に支給する仕組み)の必要性が注目されている。一方、AIが生産性の向上やデータ主導の意思決定、創造性や新しい働き方の推進につながるといった、より現実的な見方もある。
生成AIは、人間を模倣し、人間が作成したかのようなテキストやコード、画像などを生成する。これは、ディープラーニング(*深層学習)を用いた大規模言語モデル(LLM)の発展によって可能になった。OpenAIのChatGPTはこのLLMを活用した先駆的な事例であり、AIが「認識」から「生成」へと進化する契機となった。
AIエージェント(またはエージェントシステム)は、「人間と機械」をつなぐ新たなインターフェースとして予想されている。ビジネスの場面では、AIは状況を理解し、ユーザーの代わりにアクションを実行するようになるだろう。マイクロソフト社のサティア・ナデラCEOは「エンタープライズ・オーケストレーション層」(*企業のさまざまなシステムやアプリケーションを統合し、複数タスクを調整・管理する仕組み)の概念を提唱し、また、将来的にはエージェントシステムを活用するための対話型インターフェースが普及すると予測している。
しかし、AIは完璧ではない。「幻覚」と呼ばれるが、LLMが誤った情報やありえない回答を生成することもある。一方で、教育分野ではAIを活用した新しい学習方法が広がりつつある。例えば、アバターと会話しながら外国語を学んだり、生成AIを使って音楽を共同制作したりすることが可能になっている。このような変化は、職場環境にも波及するだろう。
AIが信頼されるようになれば、コールセンターのオペレーターや保険請求、会議の議事録作成など多くの事務的な仕事は消滅すると予測されている。企業にとっては、人件費削減や業務効率化、イノベーションの促進などさまざまな利益をもたらす。
また、AIは単に人間の仕事を置き換えるのではなく、人間の能力を補強することでより興味深い機会を生み出す。AIは単独で業務をこなすのか、それとも人間と共に創造するのか。作曲家はAIからインスピレーションを得るのか、それともAIが楽譜を作るのか。弁護士が契約書をゼロから作成するのか、それともAIが草案を作り、専門家が最終確認を行うのか。
かつてメカニカルタークス(*機械仕掛けのトルコ人の意味)と呼ばれる手法により、人間がデータにタグを付けることで機械学習データセットを構築しAIの世界を創造してきた。現在では、AIが膨大なデータセットを自ら処理して複雑な情報を理解するように進化している。AIは「認識」から「生成」へ、さらに「文脈化と相関性の理解」へと進化するにつれ、「解釈はできるが定義はできない」人間よりも賢くなっていく。
「人間と機械」のインターフェースも同様に興味深い。現在、私たちはチャットボットやプロンプトを使用しているが、これらは今後もテキストのままなのか、それとも触覚や音声などより自然な対話型へと進化するのか。「Siriに聞く」という概念は、音声インターフェースにあてはまる。「チャット」という名称もまた、意味のある言葉なのだ。
大規模なパーソナライゼーションもすでに現実となっている。その代表例として、ミュージシャン兼テクノロジー起業家であるウィル・アイ・アム氏が開発したAIプラットフォームがある。同氏は、「Raidio」というAI搭載ラジオ局を立ち上げ、視聴者に応じてニュースやコンテンツをパーソナライズし、好みの音楽を提供する。これは対話型の体験であり、個々のユーザーに最適化される。ただし、「エコーチェンバー」(*同じようなニュースや情報ばかりが流通する閉じた情報環境)のリスクや、ニュースやコンテンツが直線的でなく一貫性のない可能性もある。
AIの進化と並行して、もう一つの新しい現象として「デジタルツイン」の活用も進んでいる。デジタルツインは、LLMを活用して物理世界の複製をデジタル空間上に再現する。AIエージェントは、こうしたデジタルツインの統一されたデータセットを基に現実世界を理解し、意思決定を行うことが可能となる。例えば、アマゾン社のデジタルツインは4億もの商品の需要を2年先まで予測できる。企業は膨大なデータを集約し相関させることで、事業運営をモデル化し、未来を予測することができる。
デジタルツインは、医療分野では人体のシミュレーションに、不動産分野では建物の設計や運用のモデル化にも活用されるだろう。デジタルツインは、モデリングやデータ分析を通じて新たな効率化を推進するための模倣と検証の基盤を提供する。また、単なる運用の効率化にとどまらず、人間の生産性、創造性、発言、行動などすべてを取得し、人間のパフォーマンスを分析するツールとして発展する可能性がある。
AIの活用により、会議のあり方も大きく変わる。スマートネームタグやスマートスピーカータグが発言者を特定し、議事録や字幕、トランスクリプトを自動生成する。これにより、リモート参加でも誰がその部屋で話しているかを確認できるため、会議の公平性が保たれる。また、ホワイトボード上のメモや会議中の発言内容がすべて保存され、再生可能になり、重要な意思決定の過程を振り返ることも容易になるだろう。
これまで「暗黙知」が業務プロセスに役立つとされてきた。しかし、AIとデジタルツインの融合により組織全体の知見を統合することが可能になり、個人の直感や記憶に依存せず、最適な人材と最適な知識を掘り起こし、活用できるようになる。これにより、これまでにない洞察が得られるかもしれない。
AIと多様なデジタルツインの登場により、「データレイク」(*異なる形式や構造を持つ大量のデータを統合的に管理するストレージシステム)が新たな競争優位性をもたらし、「オーケストレーション」(*統合管理)が新たな経営戦略となる新時代が到来する。エージェントシステムの普及により、新しい働き方や新しいツール、そして新しい組織構造が生まれ、静的なシステムから動的なシステムへと移行していくだろう。