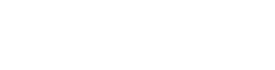ウォーカブルな都市に学ぶ、行動変容を促す空間の要素
樋野公宏/東京大学大学院 工学系研究科 都市工学専攻 准教授
コロナ禍にテレワークが定着した企業の多くでは今、「社員が自発的に来たくなるオフィス」や「自然とコミュニケーションが生まれるオフィス」、「ウェルビーイングを高めるオフィス」の構築が目指されている。オフィスをはじめとする物理環境は、人に影響を与え、行動や習慣を変えさせることができるのか。都市計画の研究者の視点から、近年医学分野でも注目されている都市と健康との関係や、歩行を促す都市の要素について解説いただき、行動変容を促す空間づくりのヒントとして提示する。

「環境には人の行動を変える力がある」という前提に立ったアプローチ
近年、社会全体の健康に広くアプローチする方法として「まちづくり」への期待が高まっています。背景には、日本社会が抱える高齢化や医療費増加などの問題に加え、個人の行動や生活習慣を変容させることの難しさがあります。
21世紀以降、医学は感染症の脅威をある程度克服し、運動不足に起因する肥満や慢性疾患が主な課題となりました。しかし、健康は個人の属性や生活習慣だけでなく、社会・経済・文化・環境的状況などのさまざまな要因により決定されるものです。たとえば「商店街が遠い」「歩道が整備されていない」「景観が魅力的でない」といった環境要因が「歩く機会の減少」という行動変容につながり、結果として健康を損ねると考えられています。そういった要因を無視して個人に「もっと歩こう」と呼びかけるだけでは限界があるのです。
私の研究テーマは「身体活動を促すまちづくり」と「犯罪の起こりづらいまちづくり」です。ゴールは違えど、どちらも個人に対する啓発や警告にとどまらず、都市の改善を通じて人々の行動に介入するというアプローチが共通しています。このアプローチはすなわち、環境には人の行動を変容させる力があるという前提に立脚したものであるといえます。
ウォーカブルな都市の要素「4Ds&2Ps」を満たすと人はよく歩く
では、歩行を促す都市とはどのようなものか。国内外の先行研究を踏まえて開発した『身体活動を促すまちづくりデザインガイド』では、歩行を促す都市の要素を4つのDと2つのPで整理しました。歩⾏者志向のデザイン(Design)、⼟地利⽤等の多様性(Diversity)、目的地へのアクセス性(Destination accessibility)、安全性等の魅力創出(Desirability)、プレイス・メイキング(Placemaking)、ソフト面での促進活動(Promotion)です。
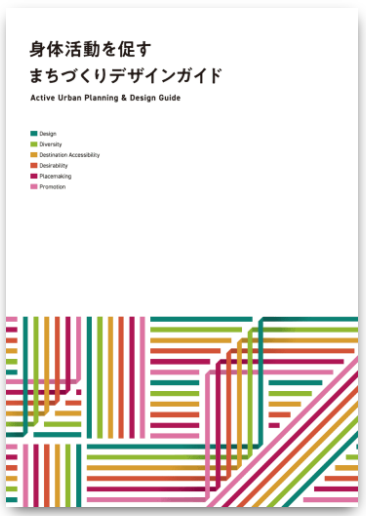
まず「Design」について、接続性の高い街路デザインは歩行を促します。具体的には、街路が碁盤状でグリッドが小さいと、目的地に最短距離で到達できるため歩きやすいといわれます。たとえばアメリカのポートランドは街区の一辺の長さが通常の半分に設計されており、歩きやすい街として有名です。また、歩道幅が広くてベンチが設置してあるような、滞在しやすいデザインの遊歩道の整備なども効果的です。愛媛県松山市の花園町通りは車道を狭めて歩道を拡幅し、イベントにも使える滞留スペースなどを配置したことで、快適に通行できるだけでなく近隣住民が休んだり集ったりできる憩いの場を形成しています。

歩行者のためのストリートファニチャーや健康遊具が豊富に設置されている。(撮影:樋野夏希)
「Diversity」は土地利用の用途の多様さを指します。純然たる住宅街よりも、カフェや店舗が混在しているまちの方が歩いていて楽しいですよね。東京は世界的な大都市には珍しく農地が多いのですが、近年その価値が見直されつつあります。我々の研究では、市民農園や体験農園の活動の参加者には健康改善などの効果がみられたのです。都市に混在する農地を非効率とみる向きもありますが、健康促進の観点でいえば保全される価値はあると思います。
「Destination accessibility」、つまり目的地となる店舗や公園、多様な施設が徒歩でアクセスできる範囲にあるか否かは、歩行活動に大きな影響を与えます。アメリカのサイト「Walk Score」はこれを評価するもので、住所を入力すると100点満点のスコアが表示されます。90点を超えると歩いて楽しい場所、25点以下なら自動車がないと生活できない場所です。日本版の「Walkability Index」も開発されていて、今後はこうした指標が不動産価値に影響を与えるようになると思われます。
都市のハード面とソフト面、両輪で歩行を促す
「Desirability」は安全性や景観などの「歩きたくなる魅力」を意味します。たとえば交通安全性は歩行を促すと考えられ、我々の分析では、歩行者専用道路、立体交差点、三叉路という3種の交通安全対策が充実しているほど、特に高齢者の歩数が多くなる傾向がみられました。また、小学生の徒歩通学についても犯罪・交通安全性や防犯カメラの設置などが促進要因となっており、安全なまちは歩きやすいまちであるといえます。このほか、まちの美化や緑化、気候に対応した歩行環境整備なども有効です。
「Placemaking」は、単なる空間(スペース)を、目的を持って訪れる場(プレイス)に変える取り組みです。まちなかに居心地のよい「プレイス」をつくる試みは全国で行われているので、『身体活動を促すまちづくりデザインガイド』の事例をご参照ください。
最後の「Promotion」は、運動習慣を楽しく継続できるようなソフト面の仕組みを指します。位置情報ゲームやランニングイベントなどを活用した多様な取り組みがあり、成功事例の一つに横浜市の「よこはまウォーキングポイント」があります。市民に配布した歩数計やアプリの歩数に応じてポイントが貯まり、商品券等が当たる抽選に参加できるというものです。リリース前後を比較した分析では、利用者は非利用者よりも月間583歩、55歳から64歳では1,891歩も多く歩いていました。自治体がこうした施策に取り組むことで、住民の健康やQOL向上に加えて医療費抑制といった効果も期待できます。

オフィスでも応用可能 多様な年代が集う場づくり
都市計画は主に屋外空間を対象としていますが、環境面から人の行動に介入するアプローチはオフィスでも応用できるのではないでしょうか。たとえば私は高齢者が地域活動に参加しやすいまちづくりについても研究しています。そこで得た多様な年代が集う場づくりの知見は、幅広い年齢のワーカーが働くオフィスづくりでも参考になるかもしれません。
多様な年代が集う場づくりというとつい「世代間の交流を促そう」と考えがちですが、実は無理に交流させなくても、同じ空間にいるだけで良い影響が生まれることがあります。ある地域の集いの場を訪問した際、子どもたちと年配の方々がお互い干渉せず別々に過ごしていて意外に感じたのですが、観察していると、子どもたちは年配者が靴を揃えているのを見て自然と倣ったり、年配者も子どもの遊びを緩やかに見守ることで好影響を受けたりしているようでした。
企業のオフィスでも、親子ほど年齢が離れている人々に無理に会話させる必要はなく、お互いが何をしているか見えて、誰にとっても居心地のよい空間にできれば十分かもしれません。そのためにはルール作りも大切です。男性高齢者50名ほどに話を聴いた研究では、退職前の役職をひけらかすようなコミュニケーションは避けるべき、というような不文律が円滑な運営に必要であることがわかりました。年代による感覚の差はあるので、緩やかなルールをいくつか決めておくことでコミュニケーションが円滑になり、居心地のよい場づくりにつながるのではないかと思います。
職も住も完結できるまちはウォーカビリティが高い
都市のウォーカビリティに関する最大の懸念は気候変動です。近年の日本の夏の猛暑は屋外活動を困難にし、人々の運動量に影響を与える可能性があります。熱中症対策を講じながら、いかに運動量を維持してもらうかが大きな課題ですが、現在のウォーカブルシティに関する議論では気候変動が十分に考慮されていません。
具体策の一つに在宅勤務の活用が考えられます。猛暑における歩行促進策としては近年、ショッピングモール内を歩く「モールウォーク」などの提案がなされ、特に高齢者の歩行促進に有効であるとみられていますが、現役世代が平日にモールウォークの時間を確保することは困難です。在宅勤務で通勤時間がなくなれば、朝の比較的涼しい時間帯に運動できますから、暑熱回避と運動のバランスをとるうえで有効でしょう。コロナ禍後は出社回帰の流れもあるようですが、在宅勤務は気候変動の文脈でも再評価されるべきだと思います。
また、暑熱回避のための在宅勤務に限らず、働く場所が徒歩圏内にあることは「Diversity」や「Destination accessibility」の観点からも都市のウォーカビリティを高めるはずです。都心への電車通勤が便利なまちは居住先として人気ですが、本来は徒歩や自転車で通えるサテライトオフィスなどがあって職も住も完結できる方が、健康面でも環境面でも電車通勤よりメリットが大きいでしょう。
このように都市計画は、今ある社会課題に応じて柔軟に考えていくべきものですが、人口減少社会においてあらゆるエリアで4つのDと2つのPをすべて満たすのは難しいと思います。道路の構成を変えるとしたら大災害の復興時くらいで、100年、200年単位の時間がかかります。ただ、もっと短いスパンで開発事業者や自治体にできることもたくさんあります。「この開発条件でウォーカビリティのために何ができるか」と少し考えてもらうだけでも、将来のまちの姿は違ってくるのかなと思います。
関連記事
理想都市のアイデアに学ぶ、日本の都市が目指すべき方向性
宇於﨑勝也/日本大学 理工学部建築学科 教授
コロナ禍で「コンパクトシティ」「職住融合」といった都市のアイデアが加速した。「課題先進国」日本の未来を考えるため、都市計画の専門家に話を聞いた。
自走する社員を育て、リモートでも一体感を保つ組織の「働く場」の現在地
ソニックガーデン
「管理ゼロ」の経営方針で知られるソニックガーデンは、組織拡大にともない働き方を変化させている。独自の人材育成施策「親方制度」の取り組みを紹介する。