自走する社員を育て、リモートでも一体感を保つ組織の「働く場」の現在地
ソニックガーデン
顧客企業のシステム開発を手掛けるソニックガーデンは、2011年の創業以来「管理ゼロ」のユニークな経営方針が話題となり、自律型組織のモデルケースとして注目を集めた。上司なし、決裁なし、勤怠管理なし、評価制度なし。2016年にはオフィスを廃止し、全社員がフルリモートで働き成果を出していた。しかし今、組織拡大にともない人材育成のフェーズを迎えたことで、働き方を少しずつ変化させてもいる。同社は「働く場」をどう捉え、どのように「自走する社員」を育てているのか。同社代表の倉貫義人氏に話を聞いた。
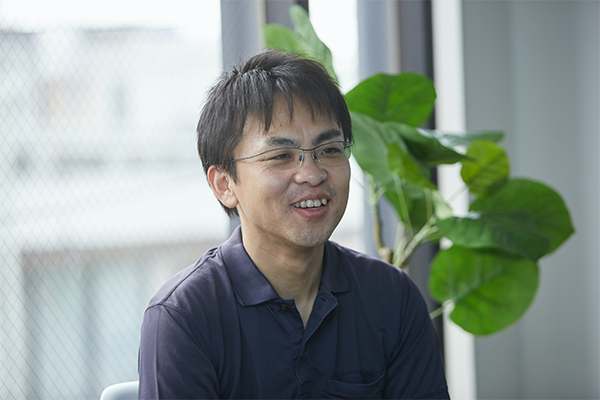
育成期間はリモートワーク禁止、「親方ハウス」に毎日通う
自由な働き方で知られるソニックガーデンだが、2021年頃から制度を大きく転換した。きっかけは、経験の浅いプログラマを新たに採用し始めたことだ。それまでは経験豊富な中途人材のみを採用していたからこそ、会社が管理せずとも各々が自律的に成果を上げていたが、新卒や経験の浅い若手社員が増えたことで人を管理・育成する必要が生まれた。
「創業10年を迎え、他社が育てた人材を刈り取るのではなく自社でも育成すべきだと思うようになりました。ただ、経験の浅い人をフルリモートで放置しても成長しようがない。能力と責任が先立ってこその自由なので、どちらも持たないうちは、不自由な仕組みのなかで育てる方が本人のためになるとわかってきました」。
そこで、プログラマ育成の仕組みとして導入したのが「親方制度」だ。入社した若手はまず親方(ベテラン社員)に弟子入りし、親方の自宅から徒歩圏内にある「親方ハウス」に毎日通ってプログラミング技術と自己管理の方法などを学ぶ。つまり、親方の居住地に引っ越すことが弟子入りの条件となる。弟子入りから3年ほどはリモートワーク禁止で、生活態度も指導される。勤怠管理をされなくなるまでにはさらに数年かかる。

技術を"見て学ぶ"ために同じ空間で働く
親方ハウスは親方が増えるたびに新設され、2025年2月時点で4拠点ある(愛知、兵庫、広島、岡山)。全国に分散する不動産管理の負担は決して小さくないが、「職人の徒弟制度と同じで、技術を"見て学ぶ"ためには同じ空間で働いた方がいい。だからと言って親方に通勤の不自由を強いるわけにはいかないので、今のやり方がベストなんです」と倉貫氏は話す。「能力ある人には自由を」という考えは創業以来一貫しており、育成期間中の社員以外は、フルリモートの自由な働き方を引き続き享受している。
親方の自宅付近で探すため、ハウスの物件を見つけるのも容易ではないが、居住性や快適性は大切にしている。愛知の親方ハウスはコワーキングスペースの一区画を借りたもので、入居時には社員自ら壁に漆喰を塗った。広島ではオフィスビルのワンフロアを借り、オフィスと寮を整備している。岡山では弟子が増えて従来のハウスが手狭になったため、土地を購入して新たな親方ハウスを建設中だ。

また、東京の田園調布にも一軒家を借りており、対面で会いたいときや地方在住者が来た際などに利用する拠点となっている。若手社員は東京で一括採用された後、弟子入りする親方が決まるまでこの東京拠点に通う。育成期間中は同じ空間で働き、昼食もほぼ毎日一緒にとることで、社内の人間関係の基礎を構築してもらう狙いだ。こうした「不自由な」働き方やその目的は採用の段階で説明し、共感した人だけが入社するため、入社後のミスマッチは起きないという。
「関係性のメンテナンス」のための社員合宿
物理的に集まることを重視する姿勢は、社員合宿などのリアルイベントの多さにも表れている。合宿は5~10名単位でほぼ毎月開催され、全員が年に1回は参加する。社長である倉貫氏はほぼ全ての回に参加しているという。
「企業のメリットは置いておいて、単純に思い出を作りたいんです。思い出は複利が効く資産だから若いうちにたくさん作った方がいい。老後に振り返る思い出がzoom画面だけなのは嫌ですよね。社員たちにも、『あのとき温泉入ったね』『一緒に壁塗ったよね』と思い出を共有できる関係であってほしいし、そうなれば一体感も自ずと生まれると思います。日々のリモートワークで希薄になった関係性を、年に1度の合宿でメンテナンスする感覚ですね」。

また、一般参加可能なハッカソンや学生向けのプログラミング合宿など、社外向けのイベントも年に数回開催している。いずれも利益は出ず、採用活動の一環というわけでもない。倉貫氏はこうした活動や合宿、親方ハウスの運用など、一見非効率にもみえる取り組みを「文化と関係資本への投資」と位置づけている。
「プログラミングを、生活の糧ではなくそれ自体を楽しむもの、つまり『文化』として昇華させたいという思いが会社経営の根幹にあるので、合宿もイベントもそのための投資と考えれば筋が通ります。本業で得た利益を使って社会関係資本を育み、プログラミングという文化を豊かにするための活動に還元しているんです。それは経営理念の『いいソフトウェアをつくる。』につながり、結果として経済的成功にもつながるものだと思います」。

自走できる社員が辞めない理由
同社の働き方、ビジネスモデル、人事制度、福利厚生などの施策はすべて「いいソフトウェアをつくる。」ために設計されている。この経営理念が社員をつなぎとめ、IT業界の人材獲得競争が激化するなかでも、ソニックガーデンは創業以来ほぼ人が辞めたことのない組織となっている。
「エンゲージメントやリテンションといった概念はあまり意識しません。採用に時間をかけて、『プログラミングは楽しい、仲間とやるともっと楽しい』と思うタイプの人に入社してもらうので、そういう人にとって快適な環境をつくっていれば『自分の居場所だ』と感じてもらえると思います。
その一環として、仕事の難易度調整は意識していますね。社歴が長い人ほど開発業務だけでは余裕になって退屈してしまうので、実力と難易度のバランスを見極めて、たとえば経営を任せたり、新人育成を任せたりして難易度を上げるようにしています。面白い仕事がある限りは、この会社で働いてもらえるので」。
リモートワーク下での人材戦略に悩む企業にとって、ソニックガーデンの取り組みは示唆に富むものだろう。単なる作業場所ではなく、「文化と関係資本を育む場」としてのワークプレイスのあり方を、同社の事例から学ぶことができる。