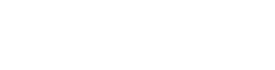パーパスを軸に働き方の多様性を認め、データに基づくオフィスの最適化
シスコシステムズ
近年、人的資本経営への注目の高まりや、不動産コストの高騰などを背景に、企業のワークプレイスは単なる執務の場ではなく経営資源と位置づけられるようになっている。アメリカにグローバル本社を置くネットワーク機器メーカーのシスコシステムズ(以下シスコ)は、企業のパーパスを軸に据えつつ、柔軟かつ合理的に変化へ対応するオフィス戦略を展開している。国内7拠点、韓国3拠点の計10拠点の管理を担う清水 正樹氏に、シスコ流のワークプレイスへの向き合い方を聞いた。

戦略として働き方の多様性を認める
シスコをはじめとする外資系IT企業にとって、オフィスはブランドの象徴であり、経営資源の一つとして生産性の高い場所が目指される。近年は各種メディアでも、生産性向上を目的に『週●日出社』を掲げ、テレワークから出社回帰へと舵を切る企業が取り上げられている。そうした企業は洗練されたオフィスデザインや豪華なアメニティを用意し、社員の出社を促す戦略をとっている。
一方でシスコは、同じく生産性を追求しながらも「各個人の働きやすさ」に比重をおく。この根底にあるのが、グローバルで掲げるパーパス『すべての人にインクルーシブな未来を実現する』だ。清水氏は「このパーパスを私の業務に当てはめると『すべての従業員にテクノロジーの恩恵を与えてより働きやすくする』ということ。特にコロナ禍以降の”働きやすさ”とは、在宅勤務を含む働き方の多様性を認めることだと考えています」と話し、戦略の中心に据えている。
多様な部署や業務がある以上、各個人の働きやすい出社頻度は一様ではない。清水氏自身は総務として社内交渉をする機会も多いため、直接顔を合わせて関係構築しておく方が仕事を進めやすいという考えのもと、毎日出社している。拘束力のある規則ではないが、業務に応じて出社目安を設定するチームもある。このように、全社で一律の出社頻度を設けるのではなく、実務に即した単位で働く場所を選べる環境が生産性につながる。また、『週●日出社』を要求する方針は離職リスクを高める可能性があるなか、他社と異なる戦略をとることで人材確保の面での効果も期待する。
「働きやすさ」に本当に必要なものを見極める
働き方の多様性を認める戦略をとりながらも、オフィスを軽視するわけではない。たとえば、オフィス見直しの際には、WELL認証(ゴールド以上)やLEED認証の取得がグローバル基準として求められており、認証取得に必要な施策を着実に実施している。「ランニング後に利用できるシャワー室など、ウェルビーイングを支える機能も備えています。ただ、現状の成熟した日本の組織に本当に必要な機能や設備は何なのか十分に吟味し、優先順位を決めています。弊社の場合、メディア受けするような奇抜なデザインや、その時代を象徴するような物や設えはなるべく避けるようにしています」と清水氏は冷静だ。続けて「レイアウトの検討やオフィス運用といった総務の施策をエンゲージメントや生産性の向上に直結させるのは難しい。できるのは、その前提となる”働きやすさ”をサポートすること」(清水氏)と語る。
その“働きやすさ”の一つに、会議や商談におけるコミュニケーションのしやすさがあげられる。会議室に導入された自社製品の高機能会議デバイスは、AIが映像の明るさや距離感を調整し発話者に自動でフォーカスする。室内のどこで話しても音声が最適化され、リモートでもリアルでも臨場感のある会議が実現する。また、ワークショップやセミナーなどを通して顧客に実際に会議体験してもらうことを意識し、大会議室やマルチに使えるスペースを多めに用意している。ここにも各種製品が導入されており、テクノロジーで働きやすさを支えることを体現する場として、顧客向けのショーケースの役割も果たしている。

契約更新時にはデータに基づいた意思決定
投資対効果を徹底的に見極める姿勢は、オフィスの契約管理にもあらわれている。「オフィスの賃貸借契約終了が近づくと次期方針を検討しなければなりませんが、日本企業の場合、オフィススペースの縮小のような施策はあまり積極的に取られず、結果として現状のスペースを引き続き利用するケースも少なくありません。シスコではこのタイミングをコスト最適化の機会と捉え、継続か移転かを本気で検討します」と清水氏。10拠点を担当するなか、取材時も3つのプロジェクトを同時進行中だと話した。
意思決定は客観的なデータに基づく分析を重視して進められている。「シスコは日本進出から約33年が経過し、現在は急速な人員拡大のフェーズではありません。また、テレワークの普及によりオフィスに必要な席数が減少したため、契約開始時と比べてオフィス面積を削減できるケースが多くなっています。部署ごとの出社率や会議室の利用データなどをもとに必要な面積を算出し、複数の方針を提案します。そのうえで、ブランド価値や利便性、機能性を維持しつつ、コスト意識の高いプランを目指します」(清水氏)。
シスコでは、世界中のすべての会議室や会議エリアに自社製のビデオ端末を設置し、オープンエリアにはアクセスポイントやカメラを配置している。これらのデバイスはすべてネットワークで連携しており、リアルタイムで各エリアの利用人数や利用時間を正確に把握できる仕組みが構築されている。この高度に統合されたオフィスインフラが、利用状況の詳細なデータを収集・分析を可能にし、客観的な根拠に基づいた意思決定を支援している。

シスコの戦略には、パーパスを軸に自社に必要なものを取捨選択する思想が、オフィスレイアウトや拠点管理に一貫して反映されていた。また、構築して終わりではなく、データを基に見直しを重ね、その時々の最適なオフィスへと柔軟に対応している。日本企業にとっても、自社の取り組みのなかに、シスコのようなデータに基づく合理的な判断を取り入れることは、ワークプレイス戦略をアップデートするヒントになるだろう。
関連記事
「家で過ごす時間を大切に」在宅勤務に舵を切った背景と、定着の工夫
LIXIL
現在、企業の出社/テレワークの方針は多岐にわたる。本記事では、テレワークを中心としたハイブリッドワークを、持続可能な働き方として定着させることに成功した事例を紹介する。
自走する社員を育て、リモートでも一体感を保つ組織の「働く場」の現在地
ソニックガーデン
「管理ゼロ」の経営方針で知られるソニックガーデンは、組織拡大にともない働き方を変化させている。独自の人材育成施策「親方制度」の取り組みを紹介する。