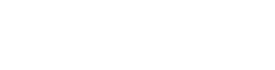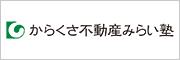2025.08.06
明日の職場が直面する10の圧力
~英国ワークテック・アカデミーによる2025年第2四半期トレンドレポート~
仕事とワークスペースをメインテーマとする世界的な知識ネットワーク「WORKTECH Academy(ワークテック・アカデミー、*1)」は、2025年第2四半期にトレンドレポート「Under Pressure: Ten top tensions facing tomorrow’s workplace(*2)」を発表した。同レポートは、職場が抱える10の主要なストレス要因を通して仕事の移り変わりを調査し、職場全体で顕在化している圧力とその対応策を検証した。
1. AI加速ギャップ
2. 地政学的混乱
3. 気候危機
4. 人材確保をめぐるジレンマ
5. 脅威にさらされるデータ
6. 崩れゆく管理職の士気
7. 高騰するエネルギーコスト
8. 感情的分断
9. 高齢人材の軽視
10. 時代遅れとなった不動産
これら10のトレンドは、急速な変化のなかで、建物はより環境に優しく、エネルギー効率はよりスマートに、データはより安全に、そして人々はよりよくサポートされる必要があるという、圧力下にある職場の姿を描き出している。
これらのトレンドは相互に排他的なものではなく、いくつかの横断的なパターンが出現している。テクノロジーの進化は職場文化の適応能力をはるかに超えており、AIの導入が組織の準備態勢を上回り、サイバー脅威への対応が追いつかないことで、AIが職場にもたらす影響は一層深刻なものとなっている。
人材や従業員のウェルビーイングもまた、危機的状況にさらされている。感情的なつながりの希薄化、人口構成の不均衡、リーダーシップ能力の低下が、職場の一体感にリスクをもたらしている。
また、AI習熟度を高め、気候変動時代への移行計画を組み込み、体験価値の高いオフィスポートフォリオを構築しているような戦略的な企業と、事後的または断片的な対応にとどまる企業とのギャップの拡大も浮き彫りになっている。
2025年後半を見据えたとき、人、場所、テクノロジーを包括的かつ体系的に連携させて行動できるかどうかが、プレッシャーの中で成長できる職場と崩れていく職場を分ける決定的な要因となるだろう。
ザイマックス総研ではレポートで紹介されている10項目のうち、「AI加速ギャップ」「脅威にさらされるデータ」「地政学的混乱」「高齢人材の軽視」「時代遅れとなった不動産」の5つの圧力に関するパートを翻訳・編集して紹介する(*3)。
1. AI加速ギャップ
組織がAIの導入を急ぐなか、そのスピードが戦略を上回っており、矛盾したアプローチが燃え尽き症候群を助長し、偏見を深め、信頼を損なっている。
AIは歴史上どのテクノロジーよりも速いスピードで普及している。ChatGPTはわずか17ヶ月で10億人の週間ユーザーを獲得した。これは、Googleが達成するのに10年以上かかったマイルストーンである。モルガン・スタンレー社は2028年までにAIインフラへの累計投資が3兆ドルを超えると予測している。しかし、導入の勢いに対して組織体制が追いついておらず、リーダーシップやスキル、企業文化にまたがる準備態勢とのギャップが露呈している。
職場では、AIが役割、ルーチン、そして期待を急速に変革している。従来は若手社員が担っていた業務が自動化され、プロンプト・エンジニアやエージェント・オーケストレーターといった新たな職種が、その定義づけも間に合わないほどのスピードで登場している。しかし、デロイト社の調査によると、現在AIを効果的に使いこなせると感じている従業員は4人に1人にすぎない。多国籍eコマース企業ショッピファイ社のように、すべての職種にAIスキルを必須とし、新規採用を承認する前にその仕事がAIでは実行できないことをチームが証明することを求める企業もある。その結果、文化的な土壌が整わないまま、チームは十分に理解していないツールの使用を迫られている。
対応は多岐にわたる。ごく一部の「フロンティア企業」は、AIを中心に業務を再設計し、ツールをワークフローに組み込み、役割を再考し、「人間とAIエージェントの比率」などの新たな指標を導入してチーム設計を進めている。例えばマイクロソフト社は近い将来、すべての従業員が「エージェント・ボス」となり、AIチームメイトを管理、訓練、指示するようになると予測している。しかし、ほとんどの組織は依然様子見の状態にあり、部門ごとにツールを個別導入し、ガバナンスは整っておらず、インテリジェントシステムの活用に適さない旧来の構造に依存し続けている。
この不均衡な状況は、AIネイティブな職場と実験段階にとどまる職場との間の溝を広げつつある。
何もしないことのリスクは高まっている。ギャラップ社によると、AIツールが明確なコミュニケーションやスキルアップ、文化的なサポートなしに導入された結果、世界中の従業員エンゲージメントは23%にまで低下し、従業員からはストレスの増加、役割の混乱、そして頼らざるを得ないシステムに対する不信感の高まりが報告されている。透明性、感情的知性、そして人間による監視への投資がなければ、組織は批判的思考を失い、不平等を助長し、長期的なパフォーマンスを損なうリスクがある。スピードを追求するあまり、AIが本来強化すべき能力を損なっているのである。
AIを単なる追加機能として扱うだけではもはや十分ではない。インテリジェントシステムが意思決定、チームのコラボレーション、パフォーマンスの測定といったプロセスに組み込まれるようになるにつれ、組織はツールだけでなく、組織構造、人材育成、そして価値観も見直さなければならない。
■組織全体でAIリテラシーを高める(*4)
加速ギャップを埋めるには、AIリテラシーを人材戦略や日々の業務全体に組み込む必要がある。これは、技術的なスキルアップにとどまらず、インテリジェントシステムがどのように仕事を形成するかについての深い理解を培うことを意味する。そのためには、従業員育成の道筋を再考すること、AIエージェントを能動的に管理する新たな役割を設計すること、そしてAIのアウトプットに責任を持って取り組むために必要な批判的思考と判断力をチームに身につけさせることが求められる。
強力なAI戦略はツールを「使いこなす力」から始まる。それは、単に使い方を知るというだけでなく、ツールに問いを立て、方向づけを行い、部門を横断して有意義に統合する自信と能力を備えることを意味する。未来に対応したワークプレイスを構築するには、人間とAIが共に学び、適応し、行動する「集合知」を前提とした設計が必要である。意図的な戦略がなければ、どれほど優れたシステムであってもその潜在能力を十分に発揮することはできない。
2. 脅威にさらされるデータ
デジタルシステムが進化し、AIエージェントに自律性が与えられるなか、従来のデータセキュリティは対応が遅れており、職場のデータはかつてないほどの脅威にさらされている。
サイバー犯罪はあらゆる業界において加速している。新種のランサムウェアやAIによって生成される詐欺、標的型データ侵害などは、これまで以上に高速かつ巧妙で、検知が難しくなっている。AIを活用したツールやデバイスの導入が進むなかで、リスクは多くの経営者の想定以上に急速に拡大している。『フィナンシャルタイムズ』によると、AIを駆使した攻撃はすでに世界のサイバー犯罪の構図を一変させているという。
重要な懸念の一つは可視性の欠如である。AIエージェントや自動化システムには多くの機密データへのアクセスが許可されているが、多くの組織はそれらのツールが何をしているのか、どの情報にアクセスできるのかを十分に把握していない。『テックレーダー』の「AIエージェントレポート2025」では、ほぼすべての企業がAIの利用を拡大している一方で、AIシステムが基幹データや業務とどのように相互作用しているかを明確に理解している企業は半数にも満たないと指摘されている。
この制御の喪失は、より根本的な弱点を浮き彫りにしている。多くの企業が依存するセキュリティモデルはすでに時代遅れである。ファイアウォールやログイン認証、安全なネットワークといった境界防御型セキュリティではもはや十分ではない。リモートワーク、モバイルデバイス、クラウドプラットフォーム、そして自律型AIエージェントの登場により、データの流れは監視しにくく、保護しにくく、悪用しやすくなっている。
同時に、攻撃者もますます巧妙になっている。AIは「企業のために」だけでなく「企業に対して」も利用されている。巧妙なディープフェイクのメールからサプライチェーンへの侵入に至るまで、悪質な攻撃者は自動化や生成ツールを駆使し、時代遅れのシステムをすり抜け、セキュリティの脆弱性を突いている。デロイト社の「AIとリスクガバナンス2025」は、特にマシンIDやシステムアクセスの管理など、基本的な安全対策において、多くの企業が対応に遅れをとっていると警告している。
経営者の多くはデータ保護の重要性を認識しているものの、依然として後手に回っている。AIシステムに対して何を許可するかに関する明確な方針を持つ企業はわずかであり、AIモデルの漏えいや将来的な量子コンピューティングによる新たな脅威に対応するための防御体制を積極的に更新している企業はさらに少ない。大手電機企業タレス社の「データ脅威レポート2025」によると、ほとんどの企業は次世代リスクに対応する高度なセキュリティ手法をようやく試行し始めた段階にあり、本格的な導入には至っていない。
その結果、顧客情報や財務記録など、企業にとって最も貴重な資産が危険にさらされている。英国NHS病理サービスプロバイダーであるシノビス社へのランサムウェア攻撃のような、最近注目を集めた情報漏えい事件は、たった一つの脆弱性が事業全体の大規模な混乱、評判の失墜、そして規制上の影響を急速に引き起こしうることを浮き彫りにしている。
■サイバーリスクを経営レベルの課題として捉える(*5)
AI導入が加速するなか、従来のサイバーセキュリティモデルはもはや適切ではない。組織は、境界防御型のアプローチから脱却し、クラウドプラットフォームやハイブリッドチーム、自律型エージェントなどが混在する現代のワークプレイス環境に適したデータ中心かつアイデンティティ認識型のシステムへと移行する必要がある。これには、マシンIDを人間ユーザーと同等の厳格さで扱うこと、AIツールに対する明確なガバナンスを設定すること、そして機密情報にアクセスできる人物やデバイスを完全に可視化することが含まれる。
最も強靭な組織は、セキュリティを戦略的意思決定に組み込み、単なるIT問題ではなく、経営レベルの課題として位置づけている。デジタルツールがより強力になるにつれ、対策を講じないことの代償はますます大きくなっている。統制、可視性、説明責任に関する新たなアプローチがなければ、組織はビジネスを駆動する情報に対する信頼と制御を失うリスクがある。
3. 地政学的混乱
地域紛争、関税をめぐる脅威、多様性や柔軟な働き方をめぐる文化的な対立が、職場にかつてない圧力をかけている。
安定したビジネス環境であれば、職場に対する地政学的な圧力は合理的な範囲内に抑えることができる。国際法、長年にわたる世界的な同盟関係、共通の価値観、そして確立された自由貿易の慣行などが、抑制要因として機能するからだ。しかし、現在、私たちが直面しているのはもはや安定した環境ではない。地政学的な変動と経済の不確実性が警鐘を鳴らしている。
新米政権がかつての同盟国を威嚇し、関税をめぐり態度を翻すようになる前から、その兆候はすでに現れていた。アーバンランド研究所とPwC社の共同調査「不動産市場の新潮流:ヨーロッパ2025年」では、地政学的混乱が今年の不動産市場に大きな打撃を与えると予測されており、回答者の83%が「ヨーロッパと中東における戦争の激化」を、77%が「ヨーロッパ経済の不安定さ」を懸念材料として挙げている。
2025年に入ってから、状況はさらに二極化している。DEI(ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン)や在宅勤務といった職場の重要な課題は、かつてないほど政治問題化されている。イーロンマスク氏が米連邦政府において効率化を推し進めるなか、主要省庁でDEI施策が次々と撤廃されたことも緊張感を高めている。その結果、組織は積極的な対応を控え、守勢に回らざるをえなくなっている。
フォーチュン500企業の85%が何らかの柔軟な働き方を導入しているなかで、在宅勤務は大西洋の両岸で保守派政治家から「ウオーク」(*)のレッテルを貼られている。
マッキンゼー社の調査によると、米国の経済政策をめぐる不確実性がコロナ禍のピーク時を上回り、過去最高水準に達している。地政学的混乱への対応は容易ではない。マッキンゼー社は大手多国籍企業に対し、「地政学的中枢センター」を設置し、関税の影響緩和に向けた行動を追跡、計画し、意思決定者を指導することを提唱している。
一方で、多くの組織は米国の政策立案者の怒りを避けるために、DEI関連資料を名称変更したり、ウェブサイトから完全に削除したりして沈黙を貫いている。企業は、嵐が過ぎ去るのを待ち、できるだけ発言を控え、従業員にも同様の姿勢を促している。
■地政学的中枢センターの設置(*6)
マッキンゼー社は、かつてない混乱のなか、企業が関税変動への場当たり的かつ局所的な対応ではなく、より長期的かつ包括的な計画への移行を支援する中央拠点の設置を提唱している。この「地政学的中枢センター」には、3つの任務を果たすための独自構造が求められる。
● まず、社内のさまざまな部門に及ぶ関税の潜在的影響に包括的に対応するための、部門横断型チームを構成する。
● 第二に、チームは複数の時間軸を見据えた体制を整え、緊急課題と長期的課題の両方に対応できるようにする。
● 最後に、独自の分析に基づく計画チームが、関税運用、在庫・サプライヤー運用、ステークホルダーエンゲージメントといった分野に関する、的を絞った取り組みを調整する。
4. 高齢人材の軽視
私たちがより長く生き、長く働くようになる一方で、職場は依然として高齢化する労働力に対応できておらず、制度的な軽視が公平性を損なっている。
高齢化は世界の労働力構造を再編成し、より長いキャリアと新たな価値観が当たり前になりつつある。EUでは2030年までに55歳から74歳が労働年齢人口の約25%を占めると見込まれており、米国でもすでに、労働者の3分の1以上が50歳以上である。しかし、職場は依然として、若年層や中堅世代を前提とした旧来のシステムで構築されている。また、政治的・文化的な反発によりDEI施策が後退するなか、高齢労働者にとって重要な支援体制が弱体化し、真に包摂的な雇用への進展が脅かされている。
高齢労働者は多層的な課題に直面している。「エイジズム」(年齢による偏見や差別)は依然として蔓延し、研修やキャリアアップ、公正な評価へのアクセスを制限している。ロンドンのブルネル大学と上海交通大学の共同研究は、テクノロジーがこれらの障壁を強化していることを示している。職場のツールやAIシステム、デジタルプラットフォームの多くは、若年層でデジタルに精通したユーザー向けに設計されており、高齢従業員の感覚、認知、そしてアクセシビリティのニーズが見過ごされている。このような現象は「AI-geism(AIエイジズム)」と呼ばれ、排除と不満を引き起こし、高齢労働者の活躍を阻害している。一方、DEIの枠組みが後退することで、高齢労働者を保護する仕組みも弱体化しており、高齢労働者は脆弱な立場に置かれている。
企業の対応は一様ではない。一部は年齢に配慮した職場設計や人間工学的な適応、柔軟な勤務形態、段階的な退職制度などに投資している。しかし、多くの企業は汎用的で画一的な制度に依存し、高齢従業員特有のニーズを満たせていない。高齢労働者との共同設計はまれであり、その結果、支援よりも排除につながる技術や施策が導入されてしまうことがある。1990年代以降、高齢者に配慮した職務は増えているものの、『高齢化経済学ジャーナル』(2022年)に掲載された研究によると、高齢労働者はそれに比例した恩恵を受けていない。この不均一な進展は、表面的な分類を超えて、具体的な障壁に取り組む必要性を浮き彫りにしている。
積極的な措置を講じなければ、経験豊富な従業員が早期に退職し、組織が持つ貴重な知見が失われるリスクがある。年齢による排除は不平等を深刻化させ、エンゲージメントを低下させ、士気に悪影響を与える。職場環境やテクノロジーを高齢者に適応させることができなければ、生産性の低下や離職率の上昇につながる可能性がある。戦略的観点からみても、これらの課題に対応しないことは、組織のレジリエンスと競争力の低下につながるだろう。
今こそ、年齢という要素を職場設計、文化、そしてテクノロジーの中核要素として捉えるべきである。具体的には、年齢と交差性(インターセクショナリティ)をDEIの枠組みに組み込み、長く有意義なキャリアを支援する包括的なAIとデジタルツールを設計し、多様な働き方や退職キャリアパスに対応できる柔軟な制度を整備する必要がある。
■高齢労働力の活躍を促すには、トップダウンによる変革が不可欠(*7)
リーダーシップは、より長い労働寿命と多世代チームに対応するために進化する必要がある。世界経済フォーラムは、組織のレジリエンスの礎石として年齢包括的なリーダーシップの必要性を強調しており、経営層全体で「長寿リテラシー」を構築することを企業に呼びかけている。具体的には、以下のようなリーダー育成が求められる。
● 年齢バイアスに挑む
● 包括的テクノロジーの採用
● 有意義な長期キャリアを支援する制度を共創する
戦略的な意思決定に年齢という要素を組み込むことで、リーダーは自社を「未来に備えた組織」へと進化させ、高齢労働者の潜在能力を最大限に引き出すことができる。この可能性を引き出し、未来の適応能力を築くには、意図的で体系的な変革が不可欠である。
5. 時代遅れとなった不動産
都心部に立地するハイパフォーマンスなオフィスと、不人気なエリアにある老朽化資産との間で、ますます格差が拡大している。
オフィス回帰の動きが加速するなか、高品質でアメニティが充実した都心部のオフィスの引力は強まり続けている。一方で、老朽化した不動産を周辺部に多く抱える企業にとっては、こうしたトレンドはますます大きな圧力となっている。
JLL社の予測によると、2030年までに世界のオフィススペースの最大70%が、改修やアップグレードをしなければ使用に適さなくなる可能性がある。しかし、多くの企業はいまだに魅力に欠ける立地にある古いビルを手放せずにいる。こうした「座礁資産」は、ESG性能やデジタル基盤、体験価値において見劣りすることが多い。一方、好立地にある新築ビルは、企業がブランド価値や人材獲得、文化の醸成を追及するなかで、入居率や賃料を上げている。
この「質への逃避」はすでに広く認識されている。CBRE社の「2024年入居テナント企業意識調査」によると、グローバル企業の65%が、より良いビルや都心の拠点へのオフィス統合・移転を積極的に進めている。また、同調査によると、高品質なオフィスで働く従業員は、そうでない従業員に比べて「職場環境が生産性とつながりを促進する」と回答する割合が30%高いことも明らかになった。
長期賃貸借契約から抜け出せない、または移転コストを正当化できない企業にとっては、取り残されるリスクが現実となっている。郊外のキャンパスやアクセスの悪いビジネスパークでは、ハイブリッドワーカーを呼び戻すことに苦戦しており、活気の乏しさや交通の不便さ、アメニティの不足が、特に若者層や都市志向の人材から敬遠される要因となっている。これは、不動産ポートフォリオの問題であると同時に、人材戦略に関わる問題でもある。二流資産に縛られた企業は、企業文化の存在感や従業員エンゲージメント、競争力を失うリスクがある。
さらに深刻なのは、空室率の上昇や価値の低下が進行する不人気な地域では、都市のバランス崩壊、インフラの未活用、都市再生の停滞など、より広範な経済的な影響に直面する可能性がある。
オーナーやデベロッパーがかつてないほどのプレッシャーにさらされるなか、統合や共用化、不人気資産の創造的再利用といった戦術的な解決策が浮上している。急速に時代遅れになりつつある地域や建物において、テナントの期待にどのように応えるかという課題に大胆に挑むことが求められている。
■スペース提供者から体験キュレーターへ(*8)
ハイブリッドワークが需要を変化させ、「質への逃避」が加速するなか、老朽化や未活用不動産を保有するオーナーやデベロッパーは、スペース提供者から体験キュレーターへと進化する必要がある。
「オフィスホテル」という概念は、高水準のサービスや充実したアメニティ、柔軟なワークプレイス環境を備え、長期賃貸借契約の縛りなしに高品質な顧客体験を求めるテナントのニーズに応えるものとして注目を集めている。これは、柔軟な賃貸条件から共有の高級アメニティ、清掃、IT、受付、コミュニティやイベントプログラムまでのサービスを完全に装備した「マネージドオフィス」という形態である。
ロンドンの不動産開発会社グレートポートランドエステーツは、このアプローチを取り入れ、従来のオフィススペースをフルサービス環境に変革し、テナント誘致と定着を図っている。同社は、ロンドン中心部の物件全体にわたり、ホテルスタイルのコンシェルジュ、イベントスペース、即時利用可能な技術基盤を含む「フルマネージド」なソリューションを提供している。
オフィスホテル運営者への転換は、オーナーにとって以下のようなメリットが期待される。
● より良い体験を通じたテナント定着率の向上
● 付加価値サービスによる賃料プレミアム
● ポートフォリオの陳腐化の予防
● スペースだけでなく、サービスに基づく新たな収益モデルの創出
- ザイマックス総研
- お問い合わせ
- ※レポート原文(英語)に対するお問い合わせ
- WORKTECH Academy(Unwired Ventures)
- E-MAIL: info@worktechacademy.com