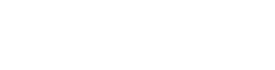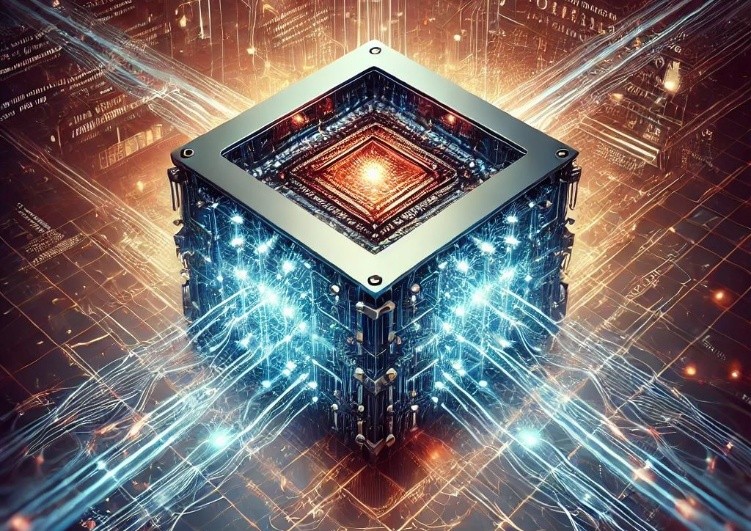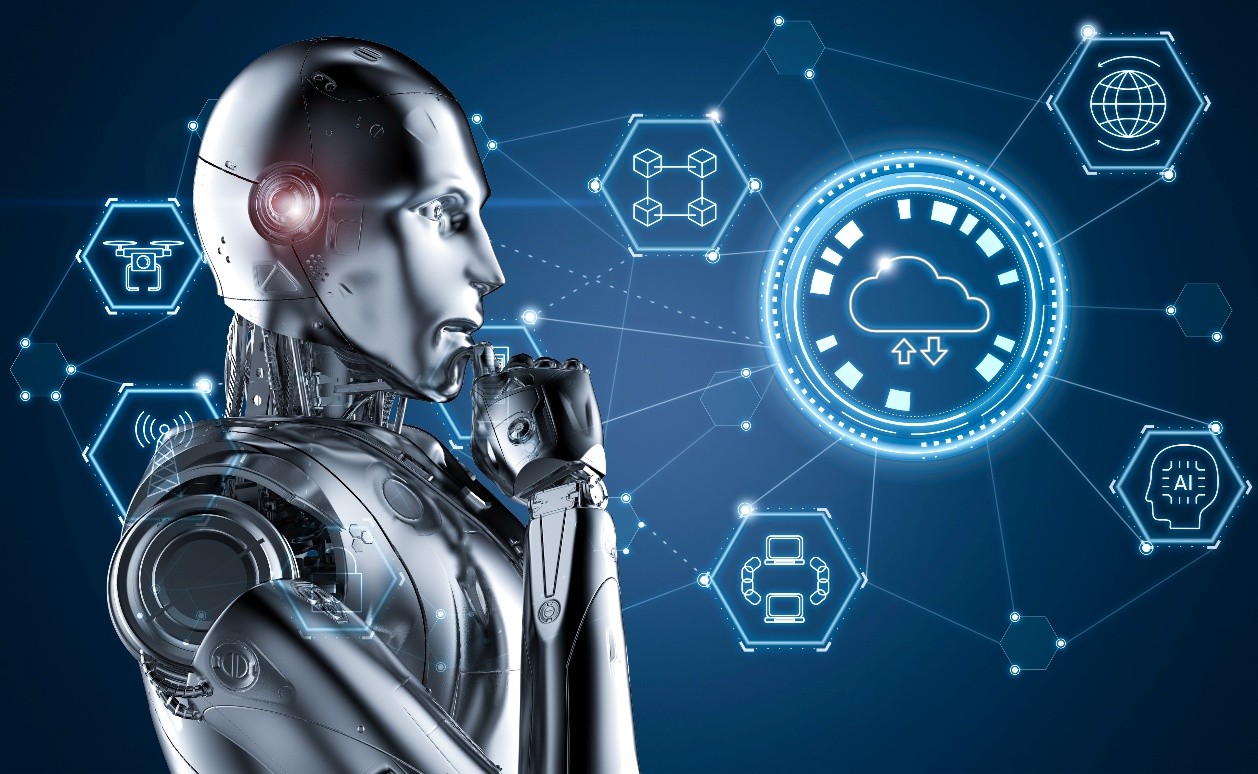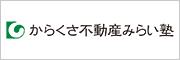2025.11.19
進化するインテリジェンス:職場のための「今」「近未来」「遠未来」のテクノロジー
~英国ワークテック・アカデミーによる 2025 年第 3 四半期トレンドレポート~
仕事とワークスペースをメインテーマとする世界的な知識ネットワーク「WORKTECH Academy(ワークテック・アカデミー、*1)」は、2025年第3四半期にトレンドレポート「Evolving Intelligence: Now, Near and Far Technologies for the Workplace(*2)」を発表した。本レポートは、原文をザイマックス総研にて翻訳・編集して紹介するものである。
デジタル革新とAIの発展が従来の知識労働のレジリエンスを試す年となった2025年の第3四半期トレンドレポートでは、仕事と職場に変革をもたらすテクノロジーに着目し、今日、明日、そして遠い未来の働き方を加速させ、場合によっては方向性そのものを変えてしまう「ゲームチェンジャー」なテクノロジーの概要を提示する。
同レポートでは、インテリジェンスの進化の道筋を「今」「近未来」「遠未来」に分類して示している。
● 今:「Embedded Intelligence(組み込み型知能)」に焦点をあてている。この段階では、テクノロジーが単なるツールから、仕事のあらゆる領域に埋め込まれたものへ移行しつつある。具体的には一元化されたダッシュボードやアプリへのデータ統合、パーソナライズされた体験、AIエージェント、説明責任を伴うAIの登場などである。
● 近未来:「Relational Intelligence(関係性知能)」を軸としている。これは、テクノロジーがシステム層から従業員のパートナーへと進化する段階である。デジタルシステムは「人のため」ではなく、「人とともに」働き、仕事を共創する。この未来では、協調センシング、次世代アクセス、量子コンピューティングなどが、空間を利用者に合わせて様々な形態へと自在に変化させる。
● 遠未来:仕事はついに空間から完全に切り離される。デジタルパートナーは、仕事と生活において遍在する存在となる。この「Cognitive Environments(認知環境)」の時代には、デジタルインターフェースや画面は消え始め、神経技術が思考を行動に変換し、音声や動作による操作が主流になる。さらに、核融合エネルギーが都市景観をも一変させ、大規模インフラが電力網に依存せずエネルギーを利用できるようになり、データセンターに低炭素電力を供給することも可能になるだろう。
1. 今:「Embedded Intelligence(組み込み型知能)」
知的システムは、いまや職場の基盤に定着している。行動を追跡するダッシュボード、ワークフローを調整するAIエージェント、シームレスな体験を実現するパーソナライゼーションツールなど、かつてはイノベーションと思われたものが、今では水面下で機能している。
1.1. 動的データ
リアルタイムダッシュボードや職場アプリは、ライブデータからパーソナライズされた意思決定を実現し、ハイブリッドワークを円滑に進めるのに役立つ
ハイブリッドワークの普及により出社パターンが予測しにくくなるなか、最適な出勤日の選択や業務に適したスペースの確保など日々の意思決定は複雑さを増している。こうした課題の解決にはデータが不可欠となっているが、データはどのように活用されるかが肝心である。リアルタイムダッシュボードや直感的に操作できる職場アプリの登場が戦略的なデータ活用のギャップを埋めている。
職場には現在、直感的なインターフェースとリアルタイムダッシュボードを備えた多様なアプリ群が導入され、ライブデータを実用的な情報へと変換している。会議室予約ツールやハイブリッド型コラボレーションプラットフォームといった仕組みにより、チーム間の可視性と連携が強化されている。
これらのインターフェースにより、従業員はデータをリアルタイムで確認し、快適性、健康状態、騒音や照明レベル、雰囲気といった条件を基に、いつ、どこで働くかを判断できる。さらに、一部のシステムは周囲の環境データから個人のウェルビーイングに関する推奨を提示し、静的な職場を動的で人間中心の環境へと進化させている。
たとえば、シスコ社は職場におけるデジタル基盤を標準化し、一貫したユーザー体験を提供している。また、同社のCisco Spacesプラットフォームでは、サードパーティのアプリの統合により機能拡張が可能となり、食堂の待ち時間の共有やデジタルサイネージコンテンツの管理、イベントの最新情報の自動配信などを実現している。これらのツールは連携や利便性を高めるだけでなく、誰と座るべきかを提案したり、ユーザーの位置情報に基づいてスペースへのアクセスを調整したりするなど、より高度なパーソナライゼーションも可能にしている。
一方で、エプチュラ社の「2025 Workplace Index(2025年ワークプレイスインデックス)」レポートによると、現在67%の企業が6〜40種類の異なる職場ソリューションを利用しており、その結果、状況は断片化している。また、3分の1以上の組織が職場データの収集・分析・報告のためだけに11人以上のスタッフを雇用しているという。
リアルタイムダッシュボードは、こうした複雑さを整理し、戦略的データ活用のギャップを埋める役割を果たす。職場のデジタル化が進むにつれ、日常的なやり取りから生じる「デジタル排気(*ログや行動履歴などデジタル空間に排出されるデータ)」は、職場の設計、運用、そして体験に関する将来の意思決定を導くための重要な資源となる。
■事例:NTTデータ、シンガポール
ITサービス企業NTTデータは、シンガポールにある10拠点のオフィスを統合し、ウェルビーイング・イノベーション・コラボレーションを軸としたスマートで持続可能な3つのワークプレイスへと刷新した。
この取り組みでは、MerakiダッシュボードやCisco Spacesなどシスコ社のテクノロジーを活用し、リアルタイムのスペース予約や環境モニタリング、ワークプレイス内のナビゲーションを実現した。
これにより、オフィスの利用状況や空気質、エネルギー使用量に関するライブデータが得られ、データに基づいた意思決定が可能になった。さらに、この変革により、従来のオンプレミス機器の90%が撤廃され、ホスティングコストは30%以上、年間エネルギー消費量は約100万kWh削減された。こうしたスマートインフラは、運用効率の最適化を支援すると同時に、従業員にとってより合理的でパーソナライズされた体験を提供する。
■統合システムの主な機能
● スマート座席予約:リアルタイムマップや利用者の嗜好・状況に基づき、最適な席や同僚の位置を動的に提案する。主要プラットフォームには、Microsoft Viva Insights、Mapiq、Smart Spaces、Cisco Spacesがある。
● ブルードットナビゲーション付きライブマップ:Wi-FiまたはUWB(超広帯域無線)を活用し、オフィス内での正確なナビゲーションと経路案内を提供する。主要プラットフォームにはMappedin、Pointr、Blue GPS、Cisco Spacesがある。
● 環境&運用ダッシュボード:空気質、稼働状況、HVAC制御などのIoTセンサーと連携し、ビルシステムを自動調整する。主要プラットフォームにはSpacewellやCisco Spacesがある。
● リアルタイムコンテキスト:位置情報に基づく通知(例:特定ゾーンへの進入を通知)、レイアウト分析、従業員への行動喚起(例:エレベーターが混雑時に階段の利用を推奨)を提供する。主要プラットフォームにはCisco Spacesがある。
● パーソナライズされた推奨:利用パターンを分析し、集中力、健康状態、コラボレーションを高めるための個別提案を行う。主要プラットフォームにはMicrosoft Viva Insightsがある。
● オールインワン体験:アクセス管理、コンシェルジュ機能、環境制御、来訪者受付、座席予約などを統合し、一つのモバイルデバイス上で完結する仕組みである。主要プラットフォームにはSmart Spacesがある。
1.2. シームレスなパーソナライゼーション
AIを活用したパーソナライゼーションは、建物全体にわたって従業員や来訪者の接点を最適化し、適応型ワークプレイス体験を実現している
職場体験のパーソナライゼーションは、会議時間の提案やコンテンツフィードの提供といった従来の機能を超え、職場を特徴づける要素へと進化している。基本的な適応機能として始まったこの技術は、AIの活用によりハイパーパーソナライズされた体験へと発展し、組織のあらゆる建物に浸透している。これは、従業員と来訪者の職場での動き方、交流、そして感覚を形づくっている。
組織との関わりが始まった瞬間から、その体験は個々に合わせて最適化される。従業員はモバイルやNFCパスを用いてシームレスに職場やシステムにアクセスでき、AIがカレンダーに基づいて会議室へ誘導したり、着席した際に個人の嗜好に合わせてワークスペースの環境を調整したりする。
来訪者にも同様のパーソナライズされた体験が提供される。デジタルサイネージで名前を表示して歓迎し、請負業者は必要なコンプライアンス文書に直接誘導され、求職者はカスタマイズされた案内と「ブルードット」ナビゲーションによって面接室へ導かれる。
これらの体験は特定の拠点にとどまらない。組織全体の施設でシステムを連携させることで、パーソナライゼーションは個人に追随し、本社はもちろん、サテライトオフィスや他都市の顧客対応拠点においても一貫した体験を提供する。リアルタイム分析とIoT統合により、環境は動的に適応し、アクセス権限を自動調整したり、重要顧客の到着をスタッフに通知したりすることが可能になる。
デロイト社の「2025 Human Capital Trends(2025年人的資本トレンド)」レポートによると、経営者の3分の2が、従業員のスキル、行動パターン、モチベーション、ワークスタイルといった要素に基づいて設計や体験をカスタマイズすることが重要だと回答している。しかし、その実現には苦戦している。過半数の経営者は従業員のモチベーションに基づいて働き方をハイパーパーソナライズするために、新たな技術を活用することが重要だと認識しているにもかかわらず、この分野で先導的な立場にあるのはわずか5%、取り組みを進めているのも17%にとどまっている。
先に述べたような要素が組み合わさることで、職場は生きたブランドの接点となり、従業員の意思決定プロセスを支援する存在となる。パーソナライズされた体験は摩擦を減らし、関係性を強化し、従業員や来訪者など、組織に関わるすべての人々のウェルビーイングを高める。
■事例:スペースのリアルタイム割り当てシステム「GoSpace AI」
GoSpace AIは、AIを活用した出社予測や業務の関連性、ダイナミックゾーニングによって、個人の嗜好やチーム関係性に合わせてワークスペースを自動で最適化する。これにより、従業員を協働者の近くに配置し、ニーズに応じてリアルタイムで調整を行い、拠点間でのシームレスなアイデンティティ管理をサポートする。
ソフトウェア企業モドラボは、GoSpace AIの空間知能を自社ワークプレイスアプリに統合することにより、モバイルファーストのパーソナライズされた体験を実現した。従業員は、自動化された席予約やワークスペース割り当てを受けられるほか、AIが提案する出社日やチームロケーションの提案の受け取り、オフィスの稼働状況や設備、交通に関するリアルタイム更新情報へのアクセスが可能になる。
GoSpace AIは、インテリジェントなワークプレイステクノロジーが、個人の嗜好や協働パターン、運用ダイナミクスに応じてグローバルな職場環境を自動的に最適化できることを示している。
■パーソナライズされた体験を支えるテクノロジー
● AIと予測分析:AIシステムは機械学習と行動データを活用してユーザーのニーズを先読みし、最適な座席の提案からスペース需要の予測、環境の自動調整までを実現する。主要プレイヤーにはGoSpace AI、Microsoft Viva Insights、Cisco Spacesがある。
● 非接触型モバイルインターフェース:モバイル認証、NFC、QRコード、アプリベースのアクセスにより、建物や座席、会議室へのシームレスな入室を実現すると同時に、パーソナライズされたチェックイン体験を提供する。主要プレイヤーにはHID Global、Brivo、Proxy、Apple WalletやGoogle Walletがある。
● リアルタイム対応のためのIoTセンサー:稼働状況や移動、空気質、照明、温度、騒音レベルを監視する接続デバイスにより、スペースは個人やチームのニーズに応じて動的に適応する。主要プレイヤーにはDensity、Siemens Enlighted、Disruptive Technologiesがある。
● クラウドベースの相互運用可能なプラットフォーム:カレンダーや通信、アクセス制御、来訪者管理、ビルシステムからのデータを統合する集中型プラットフォームであり、ポートフォリオ全体でパーソナライゼーションを拡張可能にする。主要プレイヤーにはMicrosoft Places、Appspace、Cisco Spaces、Johnson Controls OpenBlue、Mapiqがある。
1.3. エージェント経済
AIエージェントが登場し、従来の階層型組織に代わって、自律性と成長を重視した機敏な人間とエージェントのチームが構築されつつある。この潮流はキャリア形成を加速させるだろう
知能型ソフトウェアエージェントは、メールやプロジェクト管理からワークフローの自動化、情報の要約、ユーザーに代わってシステム間でのやり取りを行うことまで、日常的なツールに組み込まれつつある。企業と個人ユーザーによる導入が進むにつれ、これらのエージェントは支援ツールから、主体的に行動するソフトウェアへと進化しつつある。
オープンAI社のサム・アルトマン氏は、2025年には最初のAIエージェントが労働力に加わり、企業の生産性を大きく変える可能性があると予測している。従来の生成AIとは異なり、エージェント型AIは自律的に目標を追求し、意思決定を行い、社会的文脈を読み解きながら行動する。この新たな環境下では、仕事は変化し、従来の組織図は通用しなくなるだろう。
セールスフォース社の調査によれば、ワーカーの77%が「AIが働き方を変えている」と回答している。多くのワーカーが単なるタスク遂行者ではなく、意思決定者としての役割を期待されている。AIが専門知識を民主化するなかで、硬直した組織構造は崩れ、人間とエージェントの能力を融合させた柔軟で成果重視の体制へと移行しつつある。
エージェントが労働力に加わるにつれ、「エージェント・ボス」の台頭が見込まれる。彼らはエージェントを構築し、委任し、管理することで、自らの影響力を拡大する。誰もがAIを活用するスタートアップのCEOのように、自らのエージェントチームを率いる必要が出てくる。マイクロソフト社の調査によれば、今後5年以内に経営者の42%が「チームがAIエージェントを訓練するようになる」、36%が「チームがAIエージェントを管理するようになる」と期待している。
パフォーマンスを最大化するには、組織は適切な人間とエージェントの比率を定義しなければならない。どの業務に何体のエージェントが必要か。そして彼らを指導するために何人の人間が必要か。
アマゾン社、モデルナ社、マッキンゼー社などの企業は既に中間管理職層を削減し、人事部門とデジタル部門を統合し、ルーチン業務の自動化にAIエージェントを導入している。経営層においても新たなAIリーダーシップの役職が生まれ、長年続いてきた権限構造は変わりつつある。
今後の変化は劇的なものとなるだろうが、人間の創造性と独創性は引き続き新しい価値と機会を生み出し続けるだろう。そして、この変化に積極的に向き合う者にとって、AIはキャリアの加速装置となるだろう。
■事例:AIシフトを牽引する企業
バイオテック企業モデルナ:ルーチン業務の自動化を目指して3,000の内部GPT(Generative Pre-trained Transformer、オープンAI社が開発した会話型AIモデル)を導入した後、ITと人事部門を統合し、最高人事・デジタル技術責任者という新たな役職のもとで運営している。この取り組みは、従業員データやAIツール、体験設計を一つの戦略的基盤に統合する新たなモデルを示している。
コンサルティング企業マッキンゼー:数千のAIエージェントを導入し、プレゼン資料作成や調査結果の要約、論理検証などを支援している。現在、AIと関連技術に関するコンサルティングが同社の売上高の約40%を占めている。
大手テック企業アマゾン:中間管理職層を削減し、よりスリムでAI対応型の組織体制へと移行している。同社は生成AIやAIエージェントを含むAIインフラやツールに約1,000億米ドルを投資しており、物流、顧客サービス、広告分野に幅広く活用を進めている
多国籍eコマース企業ショッピファイ:同社CEOトビアス・リュトケ氏は、AIの活用を全社員に義務付ける方針を打ち出した。従業員が新しい採用を要求する前に、まずAIがその役割を果たせないことを証明する必要があり、またAIの活用状況は人事評価にも反映される。この方針はAIを前提とした働き方への転換を示している。
■エージェント型AIの3段階
組織ごとにAI変革の進め方は異なるが、マイクロソフト社の「2025: The year the Frontier Firm is born(2025年:フロンティア企業が誕生する年)」レポートでは、AI統合のプロセスを3つの段階として整理している。
● AIアシスト:エージェントが人の指示に応じて個別のタスクを支援し、業務の効率化や高速化に貢献する。
● AIアドバイザー:エージェントが「デジタル同僚」として参加し、意思決定を支援する洞察を提供するとともに、従業員がより価値の高い業務に専念できるようにする。
● AI自律化:人間が方向性を定め、エージェントがワークフローやビジネスプロセス全体を自律的に運用・管理する。必要に応じて人間が確認を行う。
1.4. 説明責任のあるAI
生成コンテンツが日常業務に浸透するなか、「何が本物か」「所有権は誰にあるか」を明らかにし守るための検証ツールが登場している
生成AIの活用が一般的になるにつれ、コンテンツがどのように作られ、誰が関与し、どのようなツールが使われたのかといった疑問が浮上している。これに応じて、組織は業務成果の起源をより透明化するインフラを構築し、追跡可能性、著作権の明示、説明責任を日常業務に深く関わっているシステムに組み込んでいる。
文化的な変化としても広がっている。生成ツールがチームプロセスに組み込まれるにつれ、透明性や開示に関する期待は進化しつつあり、法務やコンプライアンス、デザイン、戦略など幅広い役割に影響を及ぼしている。
目に見えない透かしから機械可読メタデータまでを含むプロビナンス(来歴)ツールは、AIと人間が協働するコンテンツエコシステムにおける信頼の基盤となっている。大学生は論文の付録でAI利用を明記し、クリエイティブチームはビジュアル資産に追跡可能なシグナルを埋め込み、編集工程では著作者と並んでツールの利用を記録し、顧客にはプロジェクトへのAI関与が伝えられる。社内ポリシーも進化を続けており、多くのチームが戦略資料や報告書、コミュニケーションにおいてどこでどのようにAIが関わったのかを明記し始めている。
機械と人間のコラボレーションがますます進むシステムでは、コンテンツに説明責任を持たせることが不可欠である。この文脈において、仕事はコンテンツ制作からコンテンツの説明責任へと移行する。来歴ツールはシステムアーキテクチャの一部となり、業務の透明性を確保する役割を担う。AIによって形づくられる職場では、信頼は検証能力、そして成果物の背後にある目に見えない作業を追跡できる能力にかかってくる。
■事例:グーグルディープマインド社の「SynthID(シンスID)」
グーグルディープマインド社が開発したSynthIDは、AI生成の画像に目に見えない透かしを直接埋め込むことで、編集やトリミング、フィルタリングなどの加工が施された後でも識別可能となるツールである。可視ラベルとは異なり、SynthIDのマーカーは耐性を持ち、機械による検出が可能であるため、プラットフォームを横断したリアルタイムのコンテンツ検証を実現する。
この技術は今後テキストや音声、動画などへの拡張も予定されており、マルチモーダルなコンテンツの来歴追跡の基盤を築くとされている。生成AIがワークフローに組み込まれるにつれ、検証はコンテンツ自体に組み込まれたプロセスになる。大量のAIコンテンツを制作またはレビューする組織にとって、SynthIDのようなツールはコンプライアンス、リスク管理、そして信頼性確保に不可欠な存在となるだろう。
■政策動向
● 中国のAIコンテンツ表示法:2025年9月から施行される中国のAI表示法では、音声や動画を含むすべてのAI生成公開コンテンツに対し、可視および不可視の識別マーカーの付与が義務付けられている。
● 欧州(EU)のAI法:EUが制定したAI法は、職場や公共領域におけるAIシステムのリスクを分類し、リスクの度合いに応じて規制を設ける「リスクベースアプローチ」を採用している。
● 米国のAIスタートアップ企業アンスロピック社の選挙運動ガイドライン:政治候補者に対し、選挙運動コンテンツやメッセージングにおけるAIの使用を明確に開示することを奨励している。
● ユネスコのAI倫理勧告:ユネスコは、AIにおける透明性、監視、説明可能性を推進する国際的な枠組みを策定し、各国のAI戦略に影響を与えている。
2. 近未来:「Relational Intelligence(関係性知能)」
今後3年間で、システムは受動的支援を超えて進化し、関係性を感知してリアルタイムで適応する「関係性知能」が台頭すると見込まれる。この段階では、量子技術を活用したコンテンツ認識型環境や協調センシングネットワークの出現により、職場はもはやプラットフォームではなく、人と共に考えるパートナーへと変わりつつある。
2.1. 協調センシング
接続デバイスは、前例のない速度と精度で予測・適応・最適化を行う協調ネットワークへと進化している
協調センシングは、従来の孤立したIoTセンサーを超えてデータを共有・検証し、相互に連携して行動するネットワーク型システムであり、それを構築することでスマートワークプレイス基盤を次の段階へと進化させる。データを単に収集してダッシュボードに報告するのではなく、協調センシングではモーションセンサー、バッジリーダー、Wi-Fiアクセスポイントなどが互いに通信し、共通の状況認識を形成する。
この変革により、デバイスやセンシングは建物全体の「共有の脳」へと進化し、ニーズを予測し、環境を最適化し、より的確な意思決定を可能にする。従来のIoTがデバイスを中央プラットフォームに接続するのに対し、協調センシングはデバイス同士、または知的システムを介して直接連携し、データを相互参照することでより高い精度と深い洞察を実現する。世界経済フォーラム(WEF)とフロンティア社の報告書では、協調センシングが2025年の新興技術トップ10の一つとして挙げられている。
職場では、協調センシングにより照明や空調、セキュリティシステムの統合管理が可能となる。モーションセンサー、Wi-Fi接続、バッジスワイプ情報を相互参照することで、在室状況を正確に把握できる。AIはこの検証済みデータセットを用いて、人の到着前に室温を自動調整したり、退出後にシステムを迅速に停止したり、最適な会議室を提案したりすることができる。Cisco Spacesはこの原理をすでに実装しており、バッジ情報とWi-Fiデータを統合して、実際の利用状況に基づき空気の質や快適性を管理している。
この仕組みは超高信頼性通信環境に依存している。4Gから5Gへの移行により測位精度は飛躍的に向上し、資産トラッキングや拡張現実ナビゲーション、精密自動化などの新たな可能性が開かれた。しかし、現在、世界で5Gにアクセスできるのは約55%にとどまっており、この通信格差の解消が今後の普及拡大の鍵となる。
さらに課題となるのが相互運用性である。複数のメーカーやプラットフォームが混在するなか、デバイス間の真の協調を実現するには、データプロトコルの標準化が不可欠である。
協調センシングはすでに交通管理や産業オートメーション、環境モニタリングなどで活用が進んでおり、今後は職場環境をより安全で効率的、かつ適応性の高いものへと進化させる技術として期待されている。
■事例:バルセロナ市のスマートシティ化
バルセロナ市では、スマートシティ化を推進するために、街路灯、ごみ箱、駐車場、バスなどに設置されたセンサーを、オープンソースの中央データプラットフォームSentiloに統合している。この協調センシングネットワークにより、人の活動状況に応じた照明制御、リアルタイムの充填状況に基づくごみ収集の最適化、渋滞緩和のための駐車誘導などが実現されている。
市の各部局間でデータを共有することで、エネルギー消費の削減、運用コストの低減、モビリティの向上、そしてデータドリブンな都市計画の高度化を支えている。現在、Sentiloはスペイン国内の300以上の自治体で導入され、10,350個のセンサーがシステムに統合されている。バルセロナ市内だけでも、Sentiloは1日あたり750万件以上のメッセージを処理しており、リアルタイムデータの拡張性とその管理能力を示している。
■協調センシングの仕組み
協調センシングを実現するには、分散型センシング、知的データ処理、そして堅牢な接続性という3つの主要な技術基盤が必要である。これらはいずれもここ数十年で大きく進化しており、協調センシングはそれらを統合することでシームレスかつ適応的で動的なエコシステムを形成する。
● 分散型センシング:家庭、職場、都市インフラ、そして地球上に広がる膨大かつ多様なセンサー群は強力な観測ツールとして機能している。これらが自律的に通信し、相互に協調できるようになれば、その力はさらに拡大する。
● エッジ(現場)における知的処理:協調センシングは、ローカルデバイスやエッジサーバーでデータを処理するエッジコンピューティングを活用し、リアルタイムで意思決定を行う。AIと組み合わせることで、システムは即座に反応し、パターンを識別し、最小限の遅延で予測をすることができる。
● 信頼性の高い高速接続:5G通信は、膨大な数のデバイスが高速かつ安定的にデータを共有することを可能にする。これにより、環境、近接性、占有状況などの多様な要因に基づき、リアルタイムで正確な意思決定を行うことができるようになる。
2.2. 次世代アクセス
アクセスシステムは静的なチェックポイントから継続的な認証プロセスへと進化し、生体認証とデジタル認証が職場インフラの一部となる
建物、部屋、システムへのアクセスのあり方は、単発的なチェックから継続的な認識へと進化している。次世代アクセスシステムは一回限りの入場ゲートではなく、生体認証や行動パターン、文脈的なシグナルを組み合わせ、継続的な対話のような仕組みで動作することで「誰が・何の目的で」をリアルタイムで判断する。
指紋や顔認証、音声認識などの生体認証は徐々に標準技術として浸透し、従来のバッジやキーパッドに取って代わりつつある。HID社の「2025 State of Security and Identity(2025年版セキュリティ・ID産業の現状)」レポートによると、企業の73%がすでに生体認証を多要素認証戦略の一部として採用している。ソーシャルプラットフォームRedditはアクセス制御への虹彩スキャン導入を検討していると報じられており、「目をスキャンしてもよいのか」といった生体認証に関する議論が社会のなかで広がり始めている。
生体認証に加え、行動認証やマルチモーダル認証システムも注目を集めている。これらの技術は人の動作、タイピングの癖、声のトーンなどを考慮し、時間の経過とともにより広範で適応性の高い個人識別モデルを構築する。
この新しいアクセスの概念では、認証は一度きりではなく、継続的に行われる。スマートフォンが安全な信号を発信して常時認証する仕組みや、姿勢、歩行速度、キーボードの操作をバックグラウンドで追跡し継続的に検証するケースもある。これらのパターンが一致すれば、物理空間とデジタル空間をまたいだアクセスはシームレスに体験できる。一方、一致しない場合は、システムが追加認証を要求したり、リアルタイムでアクセス権限を調整したりする。
エッジAI技術やプライバシー保護インフラの進展により、認証処理はクラウドに依存せずにローカルで安全に実行できるようになっている。これにより、より安全性の高いシームレスなアクセス体験が実現する。
アクセスはより応答的で、文脈に応じた知的な仕組みへと進化している。今後の課題は、職場全体において個人識別情報がどのように検知・解釈・管理されるかを設計すること、そしてそのシステムの合理性や透明性を維持することである。信頼を前提とした設計が極めて重要になる。つまり、「いつ」「なぜ」識別信号が利用されるのかを明確にし、アクセス制御を超えてデータが利用されないよう明確な境界線を設定することが求められる。
■事例:米ツール・フォー・ヒューマニティ社の虹彩認証装置「Orb(オーブ)」
サム・アルトマン氏率いるツール・フォー・ヒューマニティ社が開発したOrbは、虹彩スキャンによって個人固有のデジタルIDを生成する生体認証システムであり、2025年に米国6都市で展開されている。このIDはローカルに保存され、ブロックチェーンによって検証される。Orbはボットや生成AIが溢れる世界において、「人間であること」を証明するために設計された。
Orbは、物理・デジタル空間の両方におけるアクセス認証への活用が提案され、分散型でアイデンティティを重視したインフラの構築が期待されている。また、2025年のロンドンテックウィークでも紹介され、参加者は実際に虹彩スキャンを体験し、独自のワールドIDを取得することができた。これは、より幅広いプラットフォームにまたがる応用可能性を示唆している。
■シームレスなセキュリティソリューション
● マルチモーダル生体認証:指紋、顔、声、虹彩など複数の生体情報を組み合わせ、多層的でより不正耐性の高い認証プロトコルを構築するシステムである。
● 行動認証:動き、タイピング、システムとのやり取りなどユーザー個人の行動パターンを分析し、継続的に本人確認を行う生体認証技術である。タイピングのリズムや歩行パターン、感情のトーンなども、時間の経過とともに識別精度を高める要素となる。
● コンテキスト認証:アクセスの時間帯、場所、周囲の認証済みデバイス、あるいは現在の行動状況などを考慮し、権限を動的に調整する入退室管理システムである。
● エッジベースID認証:AIを活用し、アクセス認証の判断をクラウドではなく、端末やオンプレミス上で処理する。これにより、遅延を低減し、プライバシーを保護することができる。
2.3. 変形する空間
AIによるデータ分析と神経適応デザインが、個人の行動や嗜好を学習し、静的な不動産を動的な空間へと変えていく
オフィスはこれまで誰にでも合う画一的なモデルとして機能したことはなく、またすべての人に最適な空間を実現することも難しかった。しかし、新興テクノロジーの進展はより動的で適応的な空間への転換を後押ししている。これらの空間は、個人のニーズや嗜好に合わせてカスタマイズ可能であり、今や固定された製品ではなく再構成可能なサービスとしての空間という考え方が現実味を帯びてきている。この変革の道筋を導いているのが、データとデザインである。
ハイパーパーソナライズされた適応型ワークプレイスは、AI、センサー、神経適応デザインを活用し、レイアウトや雰囲気、インターフェースをリアルタイムで調整する。これは、人のエネルギーレベルや認知負荷に合わせて照明が変化し、集中やコラボレーションの目的に応じて空間が拡張・収縮し、ユーザーごとにトーンや言語が変わるインターフェースが実現することを意味する。生産性パターンや性格タイプなどのデータを追跡する広範なデータ分析により、ワークスペースは個人のニーズに応答できるようになり、より感情的で人間中心かつ適応的なデザインへと進化している。
コーネル大学の神経適応デザイン研究は、この未来がすでに実現可能であることを示している。同研究ではコンピュータービジョンと機械学習を用いて表情や発話を分析し、反応型デザインを通じて照明や音響、映像を自動調整することでチームの同調性と個人の集中力を高める効果が確認された。
研究はすでに現実化しつつある。旅行サービス企業ブッキングドットコムのアムステルダムキャンパスでは、座席や会議室、ロッカー、食堂の行列のセンサーデータまで統合したワークプレイスアプリが導入され、従業員が一日をシームレスに過ごせるよう支援している。また、建築事務所ザハハディドがアラブ首長国連邦(UAE)の廃棄物管理会社ビーアやドイツの家具用金物メーカーヘティヒ社と共同で、人の行動から学習する建物やポッドの研究を進めている。さらに、ミラノデザインウィーク2025でスタジオINIが発表したインスタレーション「Willful Wonder」では、人の動きにダイナミックに反応し、物理的に形を変化する環境が実証された。
リアルタイム環境調整は従業員のウェルビーイングを向上させ、動的なレイアウトは空間利用の効率化につながる。一方で、課題も依然として残る。高度にパーソナライズされたシステムはプライバシーや同意、モニタリングの許容範囲といった新たな倫理的な課題を生み出す。さらに、適応型環境を導入するには、投資、文化的受容性、既存のワークプレイス戦略やスマートインフラとの統合も求められる。
テクノロジーが成熟し、物理空間に組み込まれるにつれ、ワークプレイスは「建物」から「協働する存在」へと変わっていく。この変化を早期に受け入れる組織こそが、耳を傾け、学び、適応する環境の新たな基準を確立するだろう。
■事例:アラブ首長国連邦(UAE)の廃棄物管理会社ビーア
同社のシャルジャ市にある新本社では、AIとデジタルツイン技術を活用し、従業員や来訪者の行動から継続的に学習している。センサーがリアルタイムデータを建物の仮想モデルに送信し、人の動きや相互作用、空間の利用状況を追跡する。
AIはこれらのパターンを分析し、個々のニーズを予測して照明や温度、ワークスペースの割りあてを最適化するとともに、ナビゲーションやメンテナンスなどの業務を効率化する。この適応型アプローチは効率性、持続可能性、快適性を高め、シームレスでパーソナライズされた体験を提供すると同時に運用コストを削減する。
■カスタマイズ可能な空間を設計するためのアプローチ
● 予測ユーザーモデリング:AIや機械学習アルゴリズムがユーザーの行動、嗜好、習慣を分析する。これらのシステムは過去およびリアルタイムのデータを処理し、環境を即座に調整することができる。応用例として、利用パターンに基づいてレイアウトや機能を再構成するデジタルインターフェースや、ユーザーのニーズを予測して設定を自動調整するスマートホームが挙げられる。
● AIパーソナライゼーションモデル:協調フィルタリングやコンテンツベースフィルタリングなどの技術が、デジタルプラットフォームで広く活用されている。ネットフリックスのおすすめ機能はその一例である。これらのシステムは、更新されたユーザーデータに応じて製品やコンテンツを動的に推奨したり、インターフェースを変更したりする。
● コンテキスト認識システム:コンテキスト認識システムは、ユーザーの目標、嗜好、状況に合わせてコンテンツやナビゲーションを最適化する。これらのシステムは、行動データによって定義されたユーザーモデルをもとに、提供する情報やリンクを動的に更新する。例えば、特定の場所に入るとその地域の割引情報が自動通知されるといった仕組みがある。
2.4. 量子最適化
量子システムの安定化が進むにつれ、組織は複雑な戦略のストレステストを実施し、未来のシナリオを予測して困難な問題に対処できるようになる
量子コンピューティングはもはや理論上の存在ではない。現在は構造化と安定化が進み、スケーリングが可能となり、組織の経営戦略の中核に位置づけられつつある。ウェイクフィールドリサーチ社によると、世界の経営者の83%が最適化のために量子コンピューティングに投資しており、その約半数が1,000万米ドル以上の収益を期待しているという。
AIが高速な反復によって急速に進化するのに対し、量子技術はより緩やかで深層的な進化の軌跡をたどる。しかしその真価は速度ではなく構造の違いにある。システムは膨大な変数をモデル化し、複数の結果を同時に検証し、従来の論理では処理不能な複雑な問題を解明することを可能にする。
この技術は、職場にも新たな可能性を切り開く。たとえば、ハイブリッドワーク戦略やカーボン削減計画といった多変量シナリオを、実行前にシミュレーションエンジンで検証できる。量子技術は施策変更の波及効果をテストし、サプライチェーンの混乱をモデル化し、空間・人・デジタルシステムがプレッシャー下でどのように相互作用するかを再現できる。これにより、経営者はダッシュボードやKPIを超えて今日の意思決定が数ヶ月後、組織、市場全体にどのような影響を及ぼすかを予測できるようになる。
AIがインターフェース層に組み込まれる一方で、量子技術はその下層にある深層ロジック層となり、意思決定を反応型から創発型へと移行させる。データに対応するだけでなく、変化を予測して先回りする意思決定が可能になるのである。すでに裏側では、職場の複雑性を計算可能にする量子システムの設計が進められている。次世代のデジタルインフラにおいて、量子技術は知能を拡張し、組織が将来の不確実性に備えることを可能にする。
■事例:量子技術を活用する企業
世界最大の会計事務所デロイト:不正検知や次世代スマート工場設計における量子コンピューティングの活用可能性を探求している。AI新興企業サンドボックスAQと提携し、量子コンピューターを用いて既存の暗号を解析し、組織が抱えるデジタル脆弱性の理解とリスク軽減を支援している。
大手IT企業富士通:最先端技術研究機関バルセロナスーパーコンピューティングセンターと共同研究契約を締結し、量子コンピューティングを活用した個別化医療の推進に取り組んでいる。このプロジェクトでは多様なデータセットを活用し、精密診断医療の実現を目指す。この協業は、富士通とIBMが共同で進める疾病検出率向上を目的とした研究を補完するものとなっている。
JPモルガンチェース銀行:量子コンピューティング企業QCウェアと提携し、量子機械学習を活用してAI駆動型リスク軽減手法である「ディープヘッジング」を強化している。量子コンピューティングの導入により、従来型コンピューティングに比べてモデル学習の効率化、ヘッジ戦略の高度化、リスク削減を目指す。
■量子技術を牽引する主要プレイヤー
● グーグル社の量子コンピューティングチップ「Willow(ウィロー)」:Willowチップは、より多くの量子ビットを扱える拡張性と計算中のエラーを自動で補正する自己修正能力を備えており、従来型コンピューターでは数千年かかる計算をわずか数分で解決する。
● IBM社の量子システム「IBM Quantum Starling(IBMクアンタム・スターリング)」:2029年までに提供予定の本システムは気候変動、医薬品、最適化分野における高度なシミュレーションを実現する。これにより、企業は従来のコンピューティングの限界を超えて戦略のストレステストや長期計画の精緻化を行うことが可能になる。
● AI新興企業サンドボックスAQ:同社は、大規模言語モデル(LLM)を超える大規模定量モデル(LQM)を開発した。このモデルは、ライフサイエンス、金融サービス、サイバーセキュリティ分野における実世界システムのシミュレーションを目的として設計されている。
● 最先端技術研究機関バルセロナスーパーコンピューティングセンター:スペイン初の公開量子コンピューターを擁している。このコンピューターは完全に欧州の技術のみで構築されており、学術界と産業界の関係者がスペイン全土のハイブリッドコンピューティングリソースにアクセスできるオープンインフラを実現している。
● 量子コンピューティング企業QCウェア:クラウドベースのSaaS(Software as a Service、ソフトウェアをインターネット経由で提供するサービス形態)プラットフォーム「Forge(フォージ)」を運営し、量子ハードウェアとシミュレーションへのアルゴリズム的アクセスを提供している。また、研究開発や金融分野において従来のワークフローと量子ワークフローの橋渡しを支援するためのコンサルティング、戦略立案、パイロット導入サービスも提供している。
3. 遠未来:「Cognitive Environments(認知環境)」
今後5〜10年でワークプレイスは自律的に考え、行動する存在へと進化する。神経インターフェース、環境システム、自律エージェント、新たなエネルギーの発展により、インターフェースは姿を消し、システムはもはや入力を待たず、人の思考や感情状態に同調して予測、適応、応答するようになるだろう。
3.1. 認知インターフェース
脳と機械をつなぐインターフェースが成熟するにつれ、職場は画面操作に頼らず、人の認知をもとに動作や環境を制御できるようになる時代へと向かっている
神経技術は職場変革の最前線に急速に進出し、脳とコンピューターのインターフェース(BCI)や認知ウェアラブルデバイスは臨床ツールから思索的なデザインコンセプトへと進化している。思考は行動を指示し、環境を形成する「制御装置」であり、同時に「コンテクスト」でもある。
認知環境では、ジェスチャーやコマンド、画面を介した操作はもはや不要となる。思考すること自体が操作となる。会議は予定通りではなく参加者の精神的な集中が同期した瞬間に始まり、意図が新たな開始信号となる。神経インターフェースはログインではなく、意図によって存在を認識する。脳信号がリアルタイムで環境を変化させる。これにより、集中状態や疲労レベルに応じて不要な刺激がフィルタリングされ、照明や情報の流れが調整される。
この職場には、目に見えるインターフェースは存在しない。コミュニケーションは多層的になり、言葉によるコミュニケーションはチーム間の認識整合を保ち、神経伝達は言葉だけでは伝わらない微妙なニュアンスを補完する。従業員は思考によってシステムを操作し、行動を引き起こし、通知ではなく感覚としてフィードバックを受け取る。認知信号は単なる操作手段だけでなく、環境を適応させるためのデータにもなる。
感情状態も空間を形づくる要素となる。例えば、プロジェクトのスプリント期間中にシステムが認知的負荷の上昇を検知すると、刺激を減らしチーム全体の集中力を高める環境へと自然に切り替える。こうして感情データは物理的インフラの一形態となる。
この未来の背景には、すでに動き出している技術の潮流がある。ニューラリンク社やシンクロン社は思考制御システムを試作しており、IBM社はAIと量子コンピューティングを融合した脳チップの研究を進めている。米国の神経科学企業スターフィッシュ・ニューロサイエンスは、リアルタイムで気分を安定させるインプラントの開発に取り組んでいる。
しかし、認知がシステムに可視化されるにつれ、神経データの所有権をめぐる問題が浮上している。また、労働者は本当に読み取られることに同意できるのか、そして思考そのものが測定可能になったとき、生産性とは何を意味するのか、といった倫理的課題も問われ始めている。
認知インターフェースは、機械や空間、そしてチームが指示を待つのではなく人の思考と同期して考え、行動する職場を形づくろうとしている。
■事例:ニューラリンク社の脳とコンピューターのインターフェース(BCI)
イーロンマスク氏が率いるニューラリンク社のBCIは、神経の意図が職場の制御層になる可能性を示す初期の事例である。2025年には、麻痺のある被験者が頭蓋骨の下に埋め込まれたコイン大のチップを介して、思考だけで自分の名前を書くことに成功した。このチップは神経信号を検出し、それを外部デバイスへ無線で送信する。
現在の応用は運動機能の回復に焦点を置いているが、ニューラリンク社の長期的な目標は、人間の認知能力を拡張し、職場を含む日常のあらゆる場面で思考と機械の直接的な相互作用を実現することにある。この未来では、ワークフローは認知によって管理され、システムは思考によって操作され、共有された認知状態を通じてチームのコラボレーションが同期されるようになるだろう。
■認知インターフェース開発に取り組む企業
● ニューラリンク社:体内埋め込み型チップを開発。それにより身体の動きを完全に介さず思考だけでデジタルシステムを制御できる。
● シンクロン社:非侵襲型脳インターフェースを開発。アップルデバイスと接続し、思考によってiPhoneやVision Proヘッドセットを操作できる。
● スターフィッシュ・ニューロサイエンス社:感情状態を検知・制御するクローズドループ型インプラントを開発中。認知ウェルネスやメンタルヘルス分野での応用が期待されている。
● IBM社:量子とAI処理を組み合わせた脳チップを研究。脳活動に適応するパーソナライズされたニューラルコンピューティングアーキテクチャの構築を目指している。
3.2. 入力を感知する
インターフェースは視界から消えつつあり、音声と動作による起動が未来の職場の主要なオペレーティングシステムとなる
アップル社が年次開発者会議(WWDC)2025で発表した「Liquid Glass(リキッドグラス)」ユーザーインターフェースは、視界から姿を消すように設計された新しいビジュアル言語を提示した。環境に重ねるのではなく、環境に溶け込む。Liquid Glassの登場は、インタラクションが画面上から離れ、タッチ操作ではなくジェスチャー、近接、存在感知によって駆動される方向へと移行することを示している。
ジェスチャー、視線、音声コマンドはすでにタップやクリックに取って代わりつつある。オープンAI社と元アップル社チーフデザインオフィサーであるジョニーアイブ氏率いるデザイン会社の協働で、存在・声のトーン・意図を感知する「スクリーンレス」なパーソナルAIデバイスが構想されている。これは、画面に縛られず、物理空間に埋め込まれた次世代のアシスタントの登場を示唆している。
将来の職場では、デザインとインターフェースは新たなインタラクション形態に適応していく。ダッシュボードやパネル、メニューは姿を消し、代わりにシステムが姿勢、近接性、微細なジェスチャーを感知する。これにより、空間は活動内容に応じて個々人やチームの多様なニーズに合わせて自動調整され、ツールは集中力が高まったときに情報を提示し、注意力が低下すると自動的に消える。インタラクションは操作ベースではなく、行動ベースとなり、「常時稼働する環境との共存」が本質となる。
しかし、こうした環境制御にはリスクも伴う。明示的なリクエストなしにアクションが実行された場合、何が起動したかをどう追跡するのか。インターフェースが消えたとき、同意はどこに存在するのか。感知システムが不可視化するにつれ、制御の境界も曖昧になっていく。
未来の職場はユーザーの動きや気分、意図により敏感に反応する。従業員自身がシステムとの相互作用を認識しないこともあるだろう。しかし、システムは常にそれを認識している。バックグラウンドで稼働し続け、日常の習慣や動き、やりとり、環境の変化を学習しながら、よりシームレスでパーソナライズされた体験を創り出していく。
■事例:モデム社の空間コンピューティング概念「Terra(テラ)」
デザインスタジオモデム社が開発したこのコンセプトデバイスは、空間コンピューティングの新たなあり方を提示し、「ポストスクリーン時代」におけるデジタルシステムとのインタラクションを探求する。従来のインターフェースに依存せず、Terraは投影光やモーショントラッキング、空間ジェスチャーを用いて環境そのものをインターフェースへと変容させる。
物理的な画面やボタンを不要にすることで、Terraはユーザーが周囲の情報やツールとより直感的に関わることを促す。まだプロトタイプ段階ではあるが、ジェスチャーや空間、周囲の環境からのフィードバックが職場システムや道案内の基盤となり、物理とデジタルの境界がますます曖昧になる未来を予感させている。
■見えないインタラクションを支えるツールキット
● アップル社の「Liquid Glass(リキッドグラス)」ユーザーインターフェース:ユーザーインターフェース要素を液体のように半透明で反応性のあるものにし、インターフェースを溶解させるデザインシステムである。
● ウェアラブル神経リストバンド:ウェアラブルデバイス社が開発したAI搭載バンドは、神経信号を読み取って微細なジェスチャーを感知し、デバイスを問わずユーザー固有の操作を実現する。
● どこでも描けるペンシル:アップル社が新たに特許を取得したApple Pencil(アップルペンシル)はトラックボール型センサーを搭載し、あらゆる表面上で描画やジェスチャー操作に対応可能である。これにより、物理的なオープン空間が入力ゾーンへと変わる。
● ニューラニクス社の磁気ジェスチャーセンサー:モバイルワールドコングレス2025で発表された腕に装着する小型センサーは、微細な筋肉の動きを検知し、ジェスチャーを追跡する。
3.3. 共生する同僚
ロボットは裏方アシスタントから人間の能力を拡張する共生型チームメイトへ
数十年もの間、ロボットの活躍は裏方で加工や清掃、運搬などの反復作業に限定されてきた。しかし、AI、精密なハードウェア、感覚技術の進歩により、職場では新たな世代の自律型・人型・タスク特化型ロボットの登場が現実のものとなりつつある。
これらの具現化されたAIエージェントは、身体的な敏捷性と文脈的知能を兼ね備え、手作業を遂行し、状況の変化に対応し、さらに意思決定にリアルタイムで貢献できる。初期の導入事例では、人の動作デモンストレーションから学習したロボットが洗濯物を畳み、部屋を片付け、在庫を正確に仕分けるといった動作を実現している。感覚能力が拡大するにつれ、機械はより感覚的で適応的かつ安全に人間と協働できる存在へと進化している。
さらに、ロボットは単に人間のように行動するだけでなく、見た目も人間に近づいている。人型デザインは実用的な利点として台頭している。オフィス、倉庫、小売店舗など人間スケールで設計された空間において、人間と同じサイズの機械は、ツールやインターフェースを自在に扱える。視覚・聴覚の合図を認識するAIアシスタントから共有ワークスペースで人間と協働するロボットまで、人型デザインへの移行は、より直感的で信頼性の高い共働関係を築く方向に進んでいる。
なかでも注目すべき変化は「共生型の働き方」への転換である。これはロボットと人間が情報を交換し、互いに学び合い、共同で問題を解決する形態である。このモデルでは、機械が多様な選択肢を生成し、ワークフローを最適化し、身体能力とデジタル知性の両方を活かして人間の能力を拡張する。ワークスペースの共同設計から最適戦略の策定まで、初期の事例はこうした相互関係が新たな業務効率性を生み出す可能性を示している。
もっとも、この未来には慎重な統合が求められる。組織は共生型ロボットを職場エコシステムに導入する前に、運用上のニーズ、従業員の期待、文化的適合性を十分に検討する必要がある。今後10年はロボットが人間に取って代わる時代ではなく、人間とロボットが共に考え、共に動き、共に働く時代となるだろう。
■事例:フィギュア社の人型ロボット
米国のロボット開発企業フィギュアはAIを搭載した人型ロボットの開発を専門としている。最新の人型ロボット「Figure 02(フィギュア02)」は人間並みの器用さとAI駆動の知覚を組み合わせ、自律的に手作業を遂行する。BMW社の実証を経て、倉庫や工場での実用化が期待されている。
同社の人型ロボットは身長約168cm、体重約70kgで、20〜25kgの荷物を運搬可能。カメラ、マイク、そして5本指の器用な動きを備え、人間の空間を移動し、手作業を遂行し、自然なコミュニケーションを取れる。倉庫や工場などの職場では、人と並んで作業を行い、反復作業や重労働を担うことで、人間がより価値の高い業務に集中できるように支援する。
共通の作業を行う際には、Figure02はAIによる知覚機能を用いて人間の指示を理解し、身体的にも人間に近い構造を持つことで、人間のために設計された空間でも自在に移動できる。また、内蔵されたマイクやスピーカー、視覚言語モデルを通じて音声による指示を理解し、自然に応答することができる。
■拡張労働の段階
オーストラリアのデベロッパーミルバック社とワークテック・アカデミーの共同研究「Augmented Work - How new technologies are reshaping the global workplace(拡張された仕事:新しいテクノロジーが世界の職場をどのように変えるか)」では、拡張労働は以下の5段階に分類されている。
● 割り当て型:機械が異なるレベルの指示のもと自律的にタスクを遂行する段階。入力は主に人間のオペレーターによって行われる。
● 監視型:機械がある程度の自動意思決定を行う段階。未知の状況が発生した際には機械が警告を発し、人間が一定の監視を継続する。
● 共存型:機械が人間と並行して作業を行う段階。空間を共有し、予測の難しい人間の動きに合わせて行動できる知能が求められる。
● 支援型:機械がタスクの効率化、精度向上、品質向上を支援する段階。人間の目標を理解し、嗜好を学習できる。
● 共生型:人間と機械の協働を実現する、現在進行中の最先端段階。人間は高次の抽象的な目的や戦略的目標を設定し、機械はそれに応じた最適な出力や選択肢を提供する。
3.4. オフグリッド・エネルギー
スケーラブルな核融合技術の到来は、より持続可能でコスト効率が高く強力なエネルギー利用の道を開き、自立型ビルの実現へとつながる
数十年にわたり、核融合エネルギーは地球の脱炭素化を可能にし、同時に地球を動かすのに十分なパワーを持つグリーンエネルギーとして期待されてきた。長年の実験と推測を経て、今や核融合は実用化の現実味を帯び始めており、新たな職場インフラの基盤が整いつつある。
核融合は炭素を排出せず、放射性廃棄物も極めて少ない。水素原子をヘリウムに融合させることで膨大なエネルギーを放出する。これは太陽のエネルギー源と同じ原理である。この反応は安定かつ安全で、燃料となる原料も豊富に存在する。
各国政府はその可能性に注目し、エネルギー・気候・インフラ課題を解決する長期的手段として核融合開発に賭け始めている。英国政府は2025年に25億ポンドを投じ、全国の産業規模の研究拠点に資金を提供した。フランスの核融合実験炉ITERや米国の核融合関連企業TAEテクノロジーズなども核融合の商業化を競っている。一方、米国エネルギー長官は、エネルギー需要が供給能力を超えて急増するなか、核融合を次世代AIを支える重要な基盤技術として位置付けている。
核融合が研究段階からインフラ段階へ移行するにつれ、組織はエネルギー不足を前提に設計する必要がなくなる。代わりに、エネルギーが枯渇しないシステム、資源を奪い合わないプロセス、そして高密度コンピューティングやクリーンな製造を支える環境を構築できるようになる。
この未来では、建物はセンサーやシステム、空間をつなぐネットワークを通じて自ら電力を生成し、分配する。AIの処理は環境負荷なく継続的に稼働する。職場はオフグリッド拠点、遠隔キャンパス、さらには軌道上の研究施設にまで広がり、化石燃料や脆弱な電力インフラへの依存から解放される。
■事例:核融合エネルギー原型炉「DEMO(デモ)」
国際原子力機関(IAEA)が支援するDEMO炉は、商用発電を目的とした世界初の核融合発電所プロトタイプである。フランスの核融合実験炉ITERから得られた知見を基に、DEMOはプラズマ反応を維持するだけでなく、核融合エネルギーを送電網対応の電力へ変換することを目指している。
本炉は2040年までに建設され、21世紀後半には大規模展開とエネルギー活用が見込まれている。DEMOは単なる物理学の突破口にとどまらず、次世代の都市、産業、そして機械知能を持続可能に駆動する基盤を築くものとして位置づけられている。
■豊富なエネルギーを実現する基盤
● 小型核融合炉:産業団地、データセンター、オフグリッド型イノベーション拠点などに適した小型モジュール式核融合ユニットである。分散型の高容量エネルギー生成を可能にする。
● AIによるプラズマ制御最適化:AIとデジタルツインを活用したリアルタイムのフィードバックシステムにより、プラズマ反応の安定化やエネルギー効率の向上、拡張可能な自律的エネルギー運用を実現する。
● ゼロカーボンインフラ:核融合エネルギーで稼働するデータセンターは、コンピューティングを環境負荷から切り離し、AIトレーニングやモデリング、運用を24時間365日、グローバル規模で継続的に実行できる。
● エネルギー主権システム:組織が自らの核融合ループを構築し、エネルギーの生成、貯蔵、配分を自律的に行う仕組みである。国家電力網への依存を低減し、エネルギー耐性を高める。
- ザイマックス総研
- お問い合わせ
- ※レポート原文(英語)に対するお問い合わせ
- WORKTECH Academy(Unwired Ventures)
- E-MAIL: info@worktechacademy.com